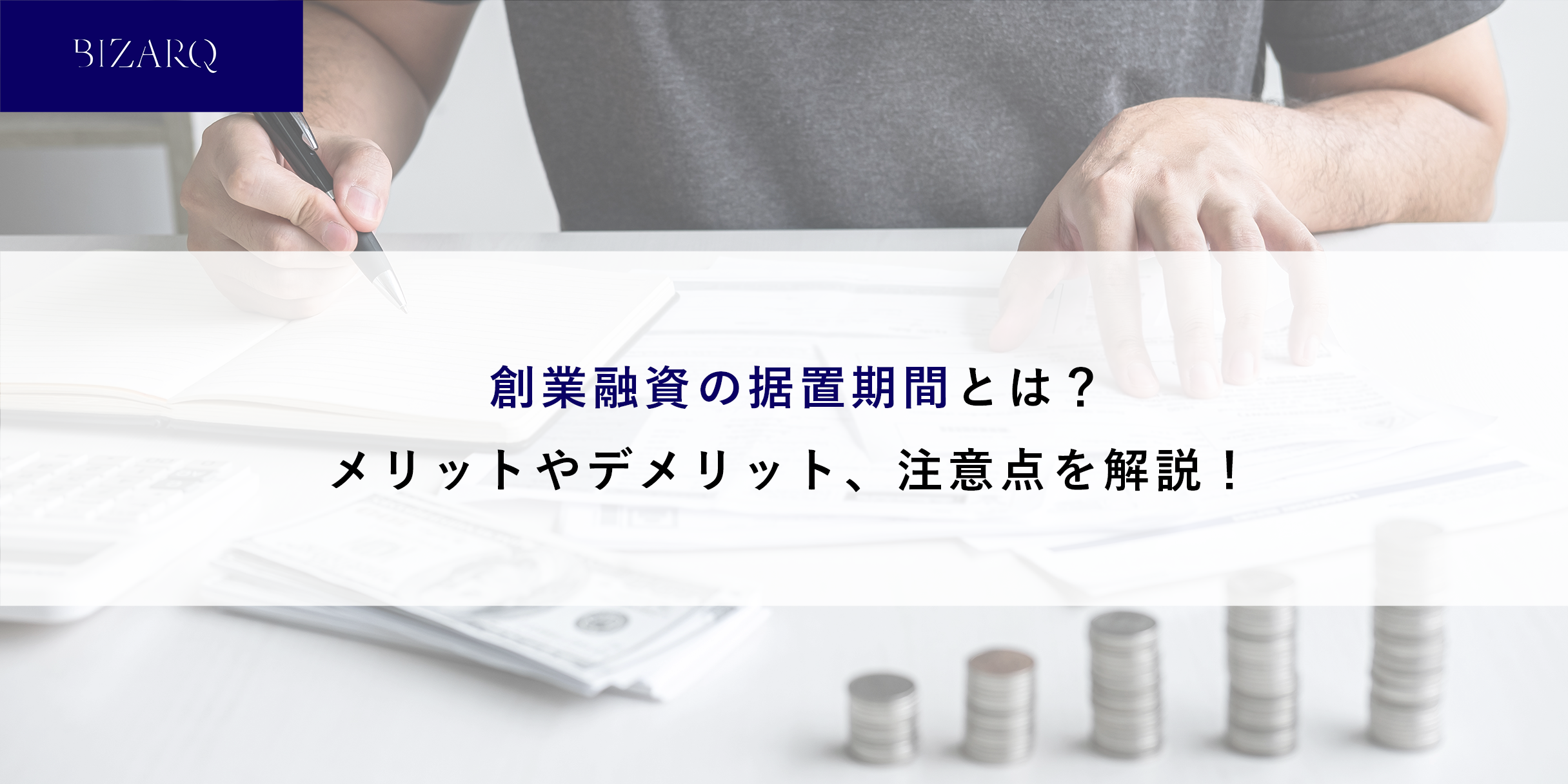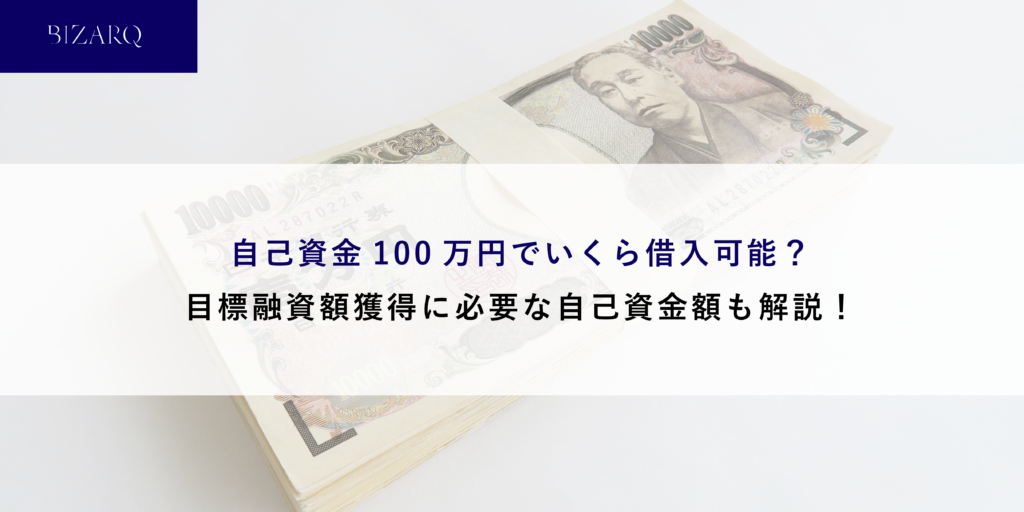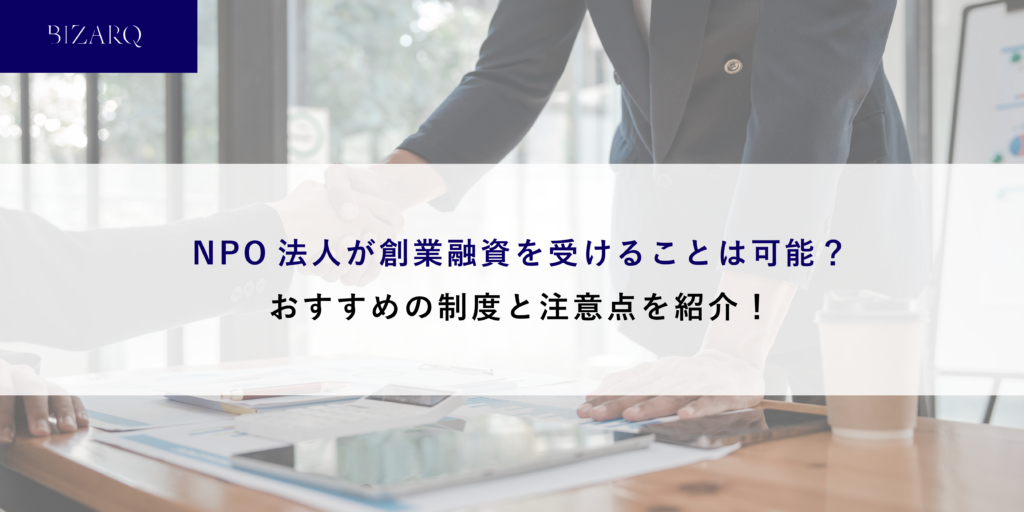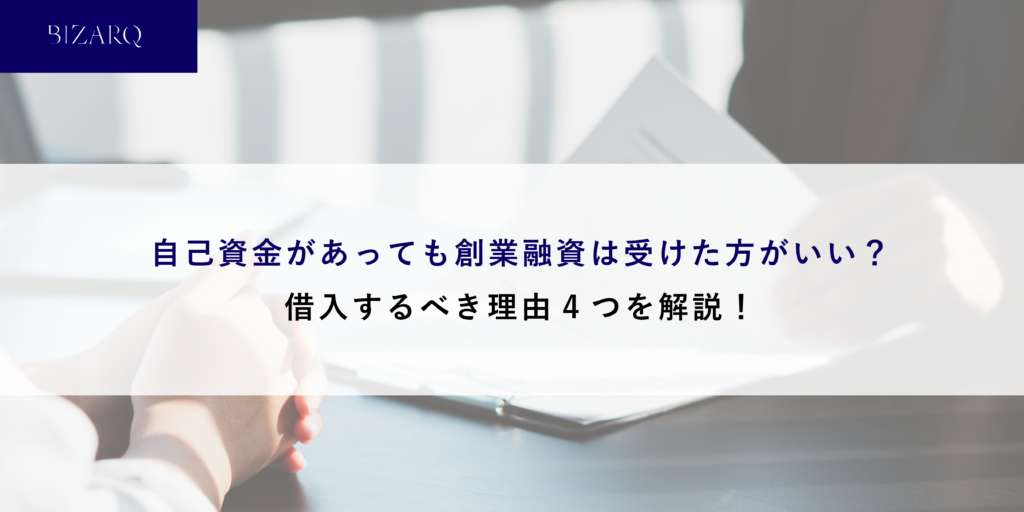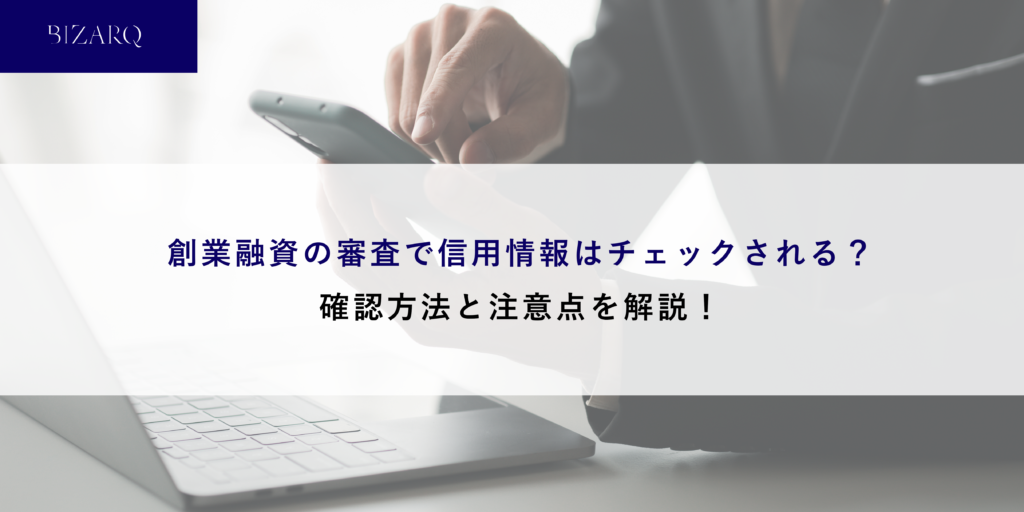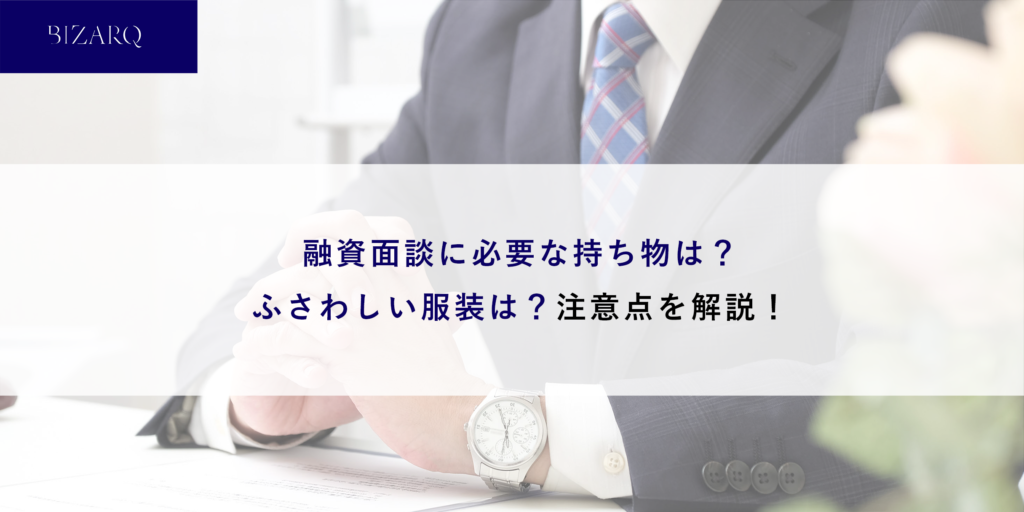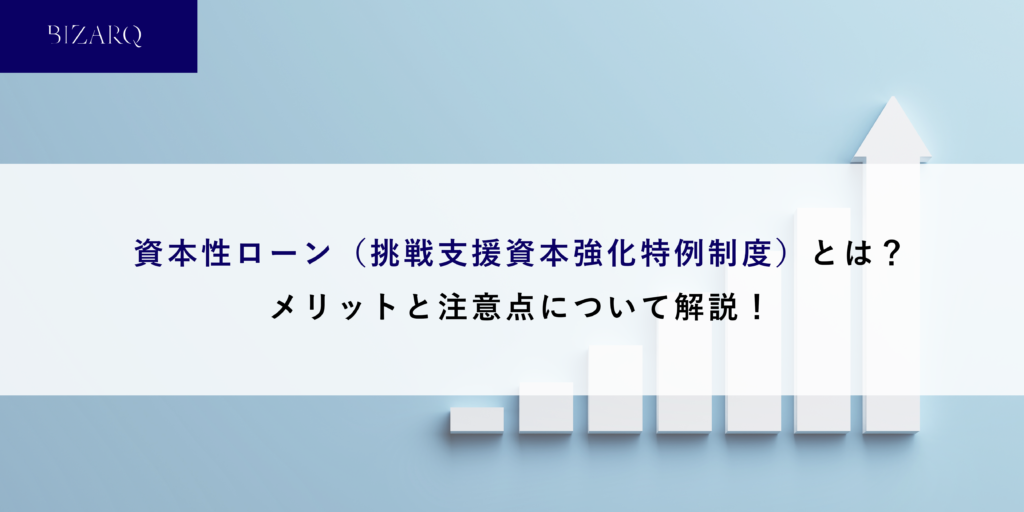
創業融資と呼ばれる融資制度の多くは据置期間の設定が可能です。
創業直後は事業が不安定で収益が発生しにくいため、据置期間を活用して返済の負担を抑えるのは効果的な手段です。
しかし、利息総額が大きくなるなど注意するべき点も存在します。
据置期間を設定するか、何年にするべきか、事前に入念な検討が必要です。
今回は創業融資の据置期間について、事前に押さえておくべきポイントを詳しく解説します。
創業融資の概要や種類については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。
CONTENTS
創業融資の据置期間 概要

まずは据置期間の概要について紹介します。
据置期間とは
据置期間とは、元金の返済をせず利息のみを支払う期間です。
日本政策金融公庫の公式サイトには「元金返済が猶予され利息だけを払い込む期間」と記載されています。
(参考|日本政策金融公庫 用語集)
日本政策金融公庫の創業融資に限らず、据置期間を設けている融資・ローンは多く存在します。
なお、据置期間は元金の返済が発生しませんが、返済期間には含まれる点に注意が必要です。
たとえば返済期間が10年、据置期間が2年の融資であれば、元金の返済は8年で行うことになります。
つまり、据置期間を設定するとその分実質的な返済期間は短くなります。
なお、据置期間の設定は任意であり、創業融資を申し込めば必ず適用されるわけではありません。
据置期間を利用したい場合は、申込時に所定の手続きを行う必要があります。
創業融資の据置期間を設定できる理由
据置期間はすべての融資・ローンで利用できるわけではありません。
しかし、創業融資に該当する融資制度は据置期間が設定できるケースがほとんどです。
据置期間を設定できる理由は、事業が安定するまでにある程度の時間が必要と考慮されているためです。
創業直後は事業が軌道に乗らず、大きな収益も発生しにくい時期といえます。
事業が不安定な時期、融資の返済は負担になる恐れがあります。
融資の返済が理由でキャッシュフローが悪化したり、大切な時期であるにも関わらず事業に集中できないといった事態も起こり得ます。
据置期間は創業直後の返済による負担を小さくし、事業に集中できる環境を作るために用意されています。
返済が負担になる恐れが大きい、融資の返済に不安を感じるという場合は、申し込みの際に据置期間の設定を希望しましょう。
据置期間は自由に設定できるわけではない
創業融資の据置期間は、創業直後の返済負担を軽くするための考慮として設けられている制度と紹介しました。
しかし、創業融資を利用する人すべてが据置期間を設定できるわけではありません。
据置期間を設定できるのは、あくまでも据置期間が必要と判断されたケースのみです。
また、据置期間を設定できる場合でも、期間の長さは希望が通らない可能性があります。
日本政策金融公庫の創業融資の据置期間は最長2年間と定められていますが、実際に据置期間として設定される期間はより短いケースが多いです。
なお、据置期間の設定を希望する場合は、据置期間を必要とする理由および期間の長さに関する根拠も提示する必要があります。
据置期間を設ける必要性がない、または据置期間の設定を希望する理由が明確でないといった場合、据置期間は却下されてしまうため注意しましょう。
創業融資の据置期間を設定するメリット

据置期間は必ずしも設定しなければならないものではありません。
そのため、利用するべきか否かお悩みの人も多いのではないでしょうか。
据置期間を設定した方が良いのかを判断をするためには、据置期間について理解を深めることが大切です。
まずは据置期間を設定するメリットを紹介します。
創業直後の資金繰りに余裕が生まれる
大きなメリットのひとつが、創業直後の資金繰りに余裕が生まれることです。
前述したように、創業直後は事業が安定しておらず収益を得られない、すなわち入金がないことも有り得ます。
そのような状況下では、融資の返済という定期的な支出は負担になる恐れがあります。
創業融資は創業に必要な資金調達のために利用する手段であるのに、返済が原因で資金繰りが悪化しては本末転倒といえます。
据置期間中は元金を返済する必要がありません。
利息の支払いは必要になりますが、元金と利息の両方を支払う場合よりは返済額がかなり少なく済みます。
日本政策金融公庫の公式サイト上で利用できる返済シミュレーション機能を使い、据置期間を設定した場合としない場合それぞれの返済額を比較しました。
以下の条件を用いています。
- ・融資額:100万円
- ・返済方法:元金均等返済、毎月返済
- ・金利:2%
- ・返済期間:5年
据置期間を設定しない場合、1年目の返済総額は218,167円でした。
一方で据置期間を1年に設定した場合、1年目の返済総額は利息のみの20,004円です。
シミュレーション結果の比較からもわかるように、据置期間中は支払い額を大幅に抑えられるため、資金繰り悪化の恐れを最小限に抑えられます。
資金の心配が少なく、事業に集中しやすい
資金の心配が少なく事業に集中しやすい点も、据置期間を設定する大きなメリットです。
前項で紹介したように、据置期間を設定するか否かによって返済額が大きく変わります。
もし据置期間を設定していなければ、創業直後で収益がない時期も毎月元利両方の支出が発生します。
返済用の資金を確保することに意識が向きすぎてしまい、創業直後の大切な時期に事業に集中できない恐れがあります。
事業のために利用した融資が原因で事業に支障が出てしまう事態が起こり得るとも表現できます。
据置期間を設定すれば、事業直後は利息だけの支払いで済みます。
利息だけであればそれほど大きな金額ではないため、資金繰りは比較的スムーズに進むでしょう。
資金の心配が少なくなる分事業に集中できるようになり、後の事業に良い影響を与える可能性が高くなります。
創業融資の据置期間を設定するデメリット
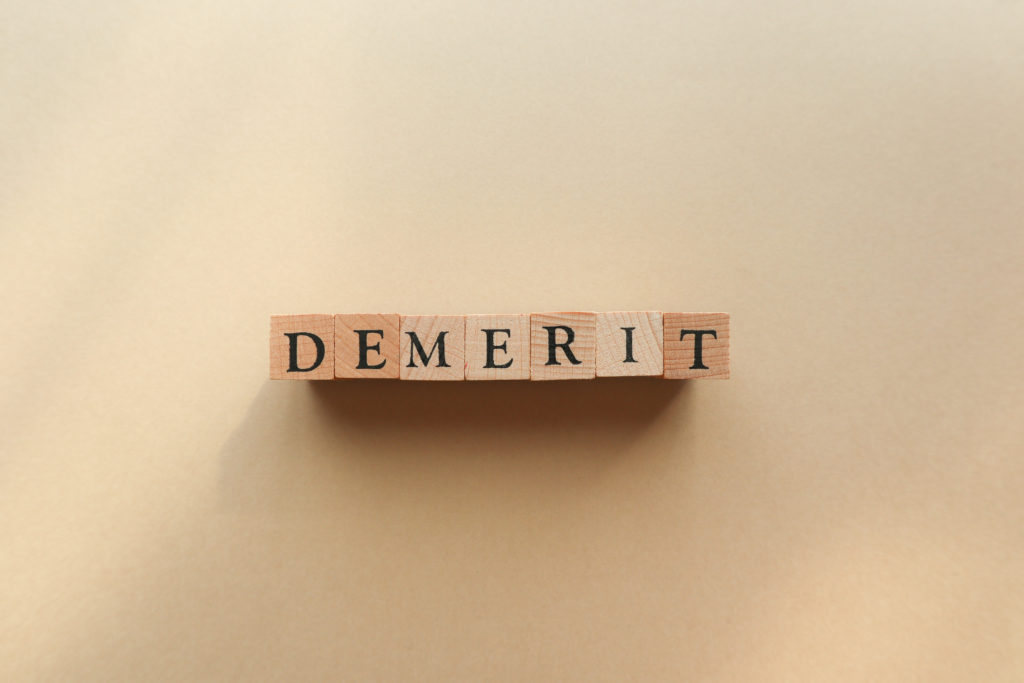
続いて据置期間のデメリットを2つ紹介します。
利息の支払い総額が大きくなる
デメリットのひとつが、利息の支払い総額が大きくなる点です。
メリットの章で紹介したシミュレーション機能を使い、据置期間を設定する場合・しない場合それぞれの返済総額を比較します。
【条件】
- ・融資額:100万円
- ・返済方法:元金均等返済、毎月返済
- ・金利:2%
- ・返済期間:5年
据置期間なしの場合、返済総額および利息総額は以下の通りです。
- ・返済総額:1,050,834円
- ・利息額:50,834円
続いて据置期間を1年に設定し、その他は同条件にすると以下の通りです。
- ・返済総額:1,060,837円
- ・利息総額:60,837円
トータルで1万円もの差が出る結果となりました。
融資額がより大きい場合や返済期間が長い場合、さらに利息総額の差が大きくなるでしょう。
据置期間中は返済の負担が小さくなるとはいえ、トータルでの負担額が大きくなる点に注意が必要です。
据置期間終了後の元金返済負担が大きくなる
据置期間を利用すると、据置期間終了後の返済負担が重くなる恐れもあります。
前述したように、返済期間が10年でそのうち2年が据置期間であれば、元金返済は実質的に8年で行うことになります。
元金返済に充てる期間が短くなれば、その分毎月の返済額が大きくなってしまいます。
据置期間は起業直後の負担を軽減する手段であり、据置期間終了後は返済負担が増える点については必ず認識しておきましょう。
創業融資の据置期間を設定する際の注意点

据置期間の仕組みやメリット・デメリットを解説してきました。
最後に据置期間の注意点をまとめます。
- ・設定が任意
- 据置期間は申し込み時に自動で設定されるものではありません。
- 利用する際は申込書への記入や所定の手続きが必要です。
- ・据置期間が長いほどトータルの利息額が大きくなる
- 利息額及び返済総額が大きくなる点にご注意ください。
- ・据置期間終了後の返済額にも注意
- 元金の返済を行わない据置期間も返済期間に含まれます。
- 据置期間が長いと、据置期間終了後の毎月の返済額が大きくなるため返済が負担になる恐れがあります。
- ・据置期間を設ける必要性について根拠の提示が求められる
- 据置期間は自由に設定できるわけではありません。
- 据置期間を設定する理由および期間の長さについて根拠の提示も求められます。
このように注意点はありますが、大切なのはデメリットを押さえた上で、メリットを活かせるように上手く使うことです。
収支計画やシミュレーションに基づき、適切な据置期間を設定しましょう。
まとめ
創業融資の据置期間を設定すれば、創業直後の事業が不安定な時期における返済の負担を小さく抑えられます。
資金繰りの心配がなくなり、事業に集中できるでしょう。
一方で返済総額や据置期間終了後の負担増大など、デメリットに注意が必要です。
据置期間のメリット・デメリットそれぞれをしっかり押さえた上で、自分にとって適切な使い方をする必要があります。
ただし、融資の申し込みがはじめての人が、自分にとって適切な期間を設定するのは非常に困難です。
事業計画やシミュレーションを正しく行うためにも、融資や事業に関する深い知識およびノウハウが必要となります。
創業融資について疑問や不安があれば、融資支援に強い専門家のサポートを受けるのが安心です。ぜひお気軽にご相談ください。
経営判断を迅速にサポート
創業融資・補助金申請はBIZARQにお任せください。
全国オンライン対応・ご相談は無料です。

記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士