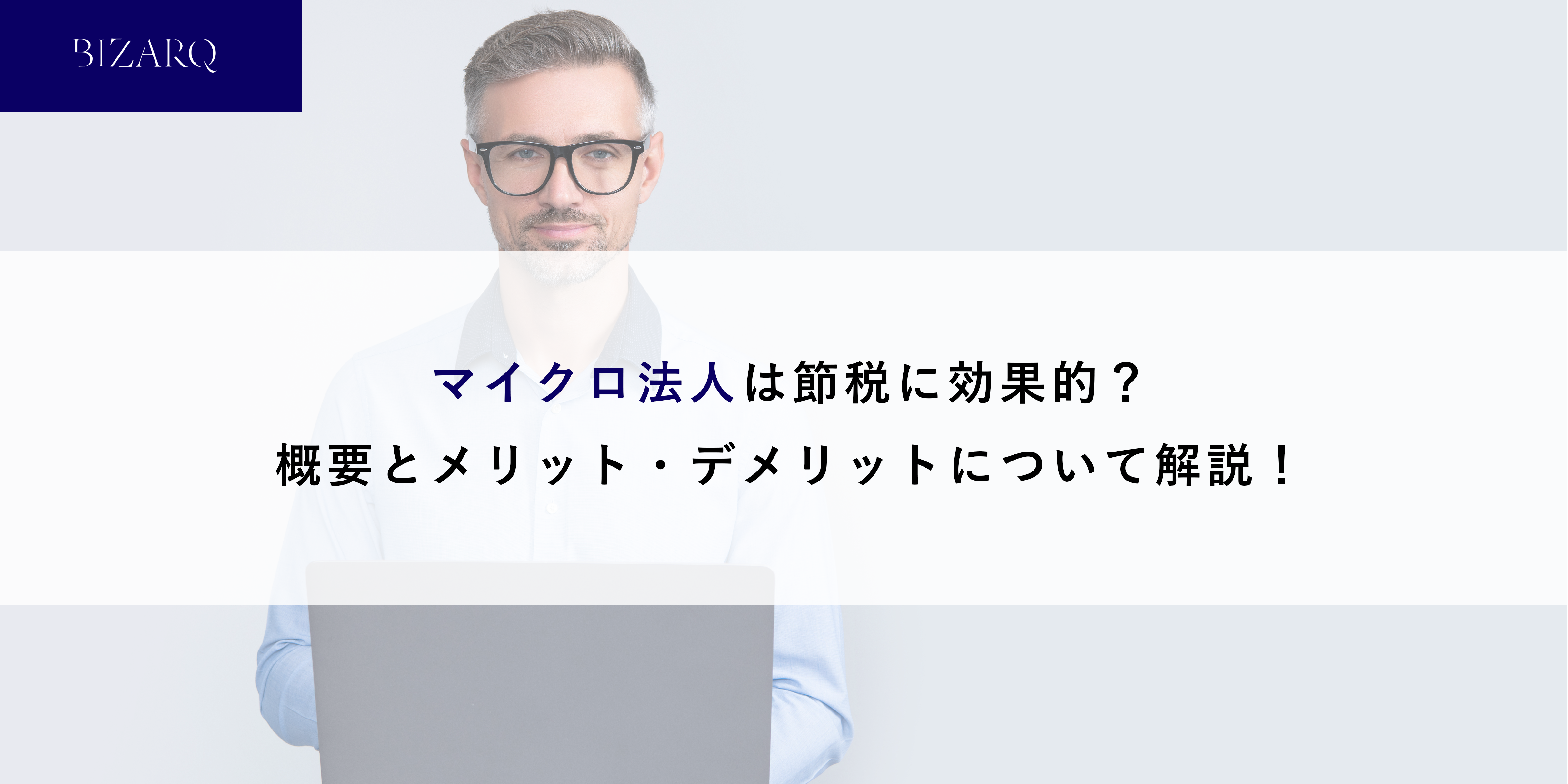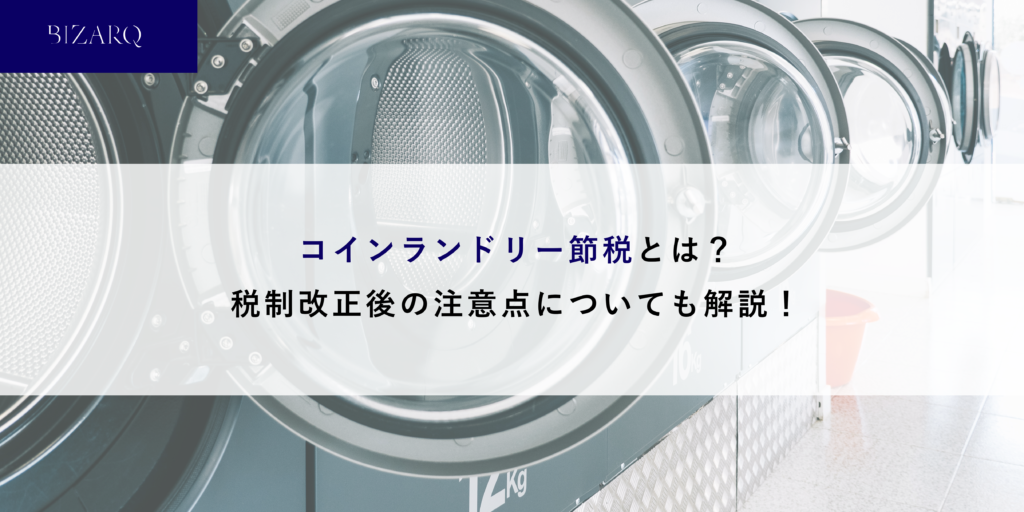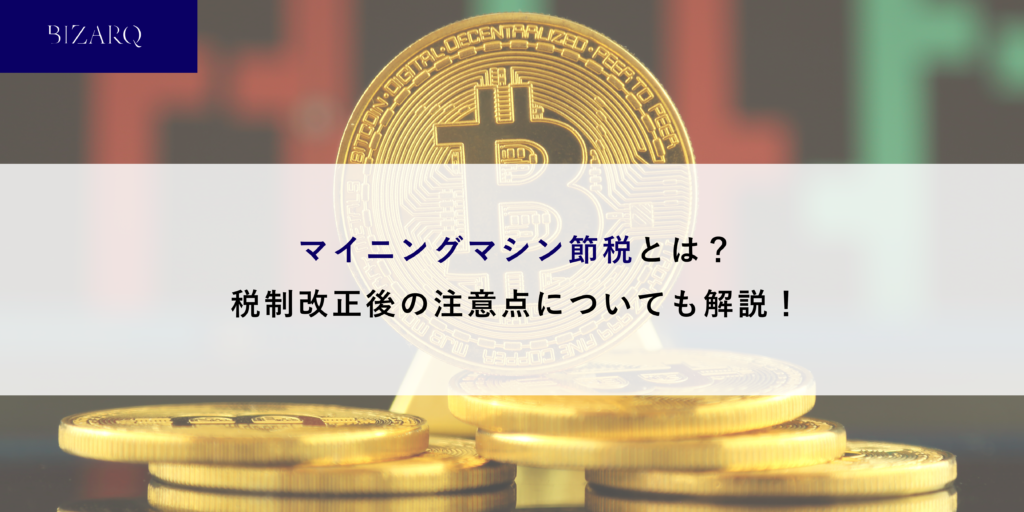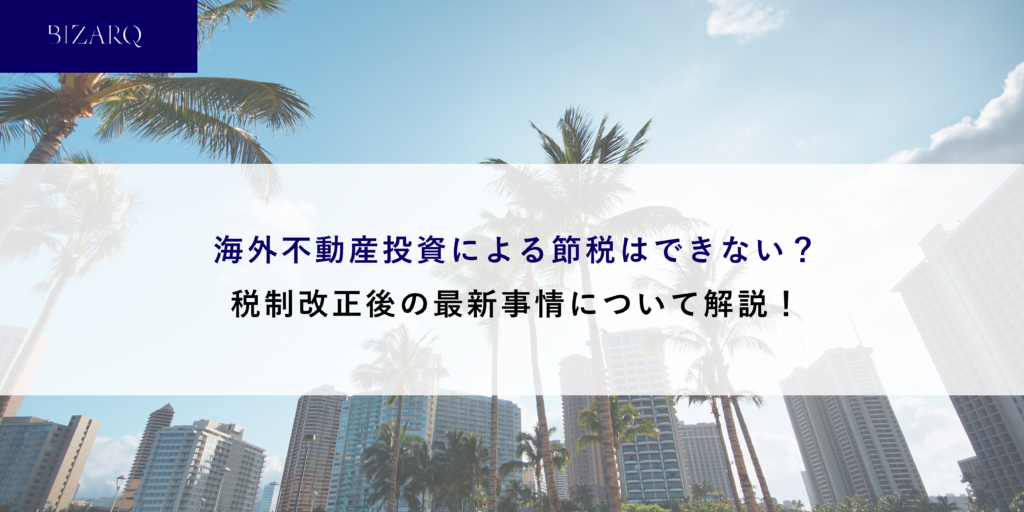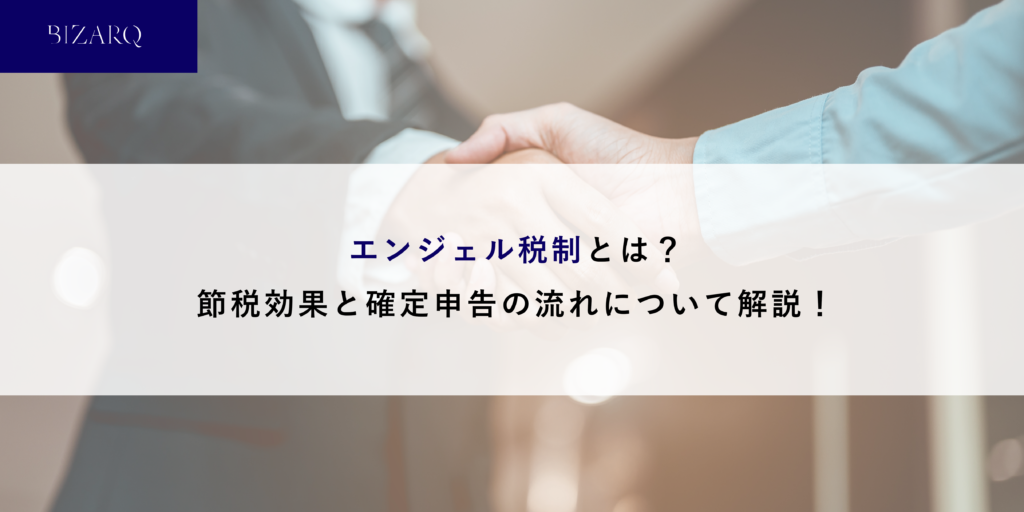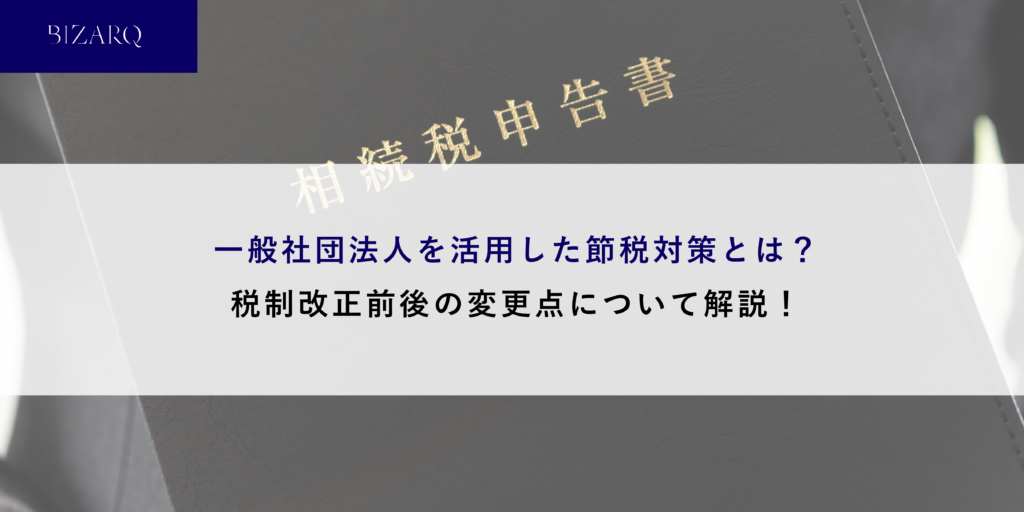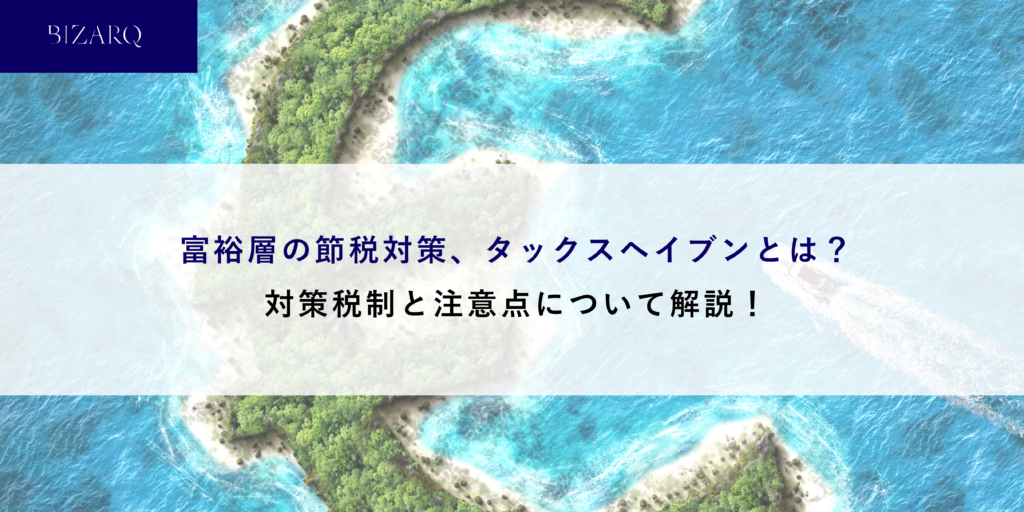
マイクロ法人とは、社長1人で経営する会社のことです。ほかの従業員や株主は存在しません。
一般的に個人事業主の節税目的で設立されるものであり、個人事業主のための会社と表現できます。
マイクロ法人を上手く活用すれば、個人事業主のままでいる場合と比べて大きな節税効果を得られます。
ただし、会社になる以上、手続き面での負担が増えたり、個人事業主にはないコストがかかる等のデメリットにも注意が必要です。
今回はマイクロ法人について、節税効果を中心に詳しく解説します。
以下の記事では個人事業主が法人成りするのに適したタイミングについて解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。
CONTENTS
節税効果を見る前に|マイクロ法人の概要

節税効果について詳しく見る前に、まずはマイクロ法人の概要を紹介します。
マイクロ法人とは
マイクロ法人とは、社長1人で経営する会社のことです。ほかの従業員や株主は基本的に存在しません。
主に個人事業主の節税目的で設立される会社であり、個人事業主のための会社と表現できます。
一般的な会社との違い
マイクロ法人と一般的な会社の大きな違いとして2つ挙げられます。
1つ目は、会社に在籍するのが社長1人だけである点です。
ほかの役員や従業員はもちろん、社長以外の株主も存在しません。
会社の経営や意思決定をすべて社長1人で行います。
2つ目は、事業拡大をほとんど追求しない点です。
一般的な会社は、程度の差はあるものの事業拡大を追求します。
個人事業主が「法人の方が事業拡大をしやすいから」と法人成りをするケースも多くみられます。
一方、マイクロ法人を設立する目的はあくまでも節税です。
仮にその時点では社長1人の場合でも、事業拡大を目的に設立した会社の場合は、一般的にマイクロ法人と呼ばれません。
マイクロ法人の主な形態
マイクロ法人の主な形態は、株式会社または合同会社です。
それぞれの特徴とメリット・デメリット、設立費用について紹介します。
株式会社
株式会社は株式の発行により株主から資金調達を行ない、その資金を基に運営する会社形態です。
出資者と経営者が異なる点が特徴として挙げられます。
株式会社の大きなメリットは、現在設立できる会社形態の中で最も社会的信用度を得やすい点です。
株式会社は決算公告が義務付けられており外部から会社の情報を把握しやすいため、結果として信用を得やすいといえます。
デメリットとしては、決算公告が義務づけられているために手間がかかる点や、会社設立および運営のコストが高い点が挙げられます。
会社設立費用は定款の種類や専門家へ依頼するか否かによって左右されますが、25~30万程度が相場といえます。
合同会社
合同会社は持分会社の一種で、出資者と経営者が必ず同じです。
株式会社と同様、出資者全員が有限責任社員となります。
合同会社の大きなメリットは、経営上必要な事務作業が株式会社よりも少なく手間が小さい点です。
株式会社と違い合同会社では不要な作業の例として、決算公告や株主総会が挙げられます。
一方、社会的信用度が株式会社より低く融資や助成金といった資金調達の難易度が高い点がデメリットとして挙げられます。
会社設立費用の相場は11~17万円程度と、株式会社に比べて非常に安価です。
マイクロ法人が節税につながる理由

続いて、マイクロ法人が節税につながる理由について詳しく解説します。
所得が大きいと法人税の方が金額を抑えられる可能性が高い
所得額が大きい場合、個人事業主にかかる所得税よりも法人にかかる法人税の方が税額を抑えられる可能性が高いです。
所得税は超過累進課税を採用しており、所得が一定を超えた部分に対し、より高い税率が適用されます。
つまり、所得額が増えるほど税額が高くなる仕組みです。
一方で、法人税は所得に関係なく税率が一定となります。
そのため、所得が一定を超えると所得税より法人税の方が税額を抑えられるのです。
経費にできる支出が多い
事業内容が同じでも、個人事業主よりも法人の方が経費にできる支出が多いです。
法人のみが経費にできる支出の具体例を紹介します。
- ・経営者本人の役員報酬
- 個人事業主は自身の報酬という概念がないため、法人ならではの経費といえるでしょう。
- ただし、役員報酬に関する一定のルールに従う必要があります。
- ・出張手当
- 個人事業主の出張で経費として認められるのは、実際にかかった交通費や宿泊費のみです。
- 法人であれば出張旅費規定を作成することで日当や出張手当の支給ができ、経費計上も可能です。
- ・慶弔見舞金
- 慶弔規程を作成すれば、冠婚葬祭の費用や見舞金・出産金・結婚祝いなども経費計上ができます。
- ・退職金
- 法人の場合、退職金の損金計上が可能です。ただし不当に過大な額は認められない恐れがあります。
- ・生命保険料
- 法人名義で生命保険に加入すれば、保険料の経費計上が可能です。
マイクロ法人を設立すれば計上できる経費の額が増え、結果として所得を抑えられる可能性があります。
ただし、経費計上に際して細かなルールが設定されているものも多いため、事前の確認が必要です。
欠損金の繰越期間が長い
法人は欠損金(赤字)の繰越期間が長く設定されています。
前提として、個人事業主も青色申告であれば欠損金の繰り越しが可能です。
たとえば2023年度に50万円の赤字、翌年2024年に80万円の黒字となった場合、2023年の赤字と相殺して2024年を30万円の黒字にできます。
ただし、個人事業主が欠損金を繰り越せる期間は最長3年間です。
欠損金の額が大きい場合、繰越期間である3年の間に相殺しきれない恐れがあります。
一方で法人は、最長10年間にわたって欠損金の繰り越しができます。
欠損金の繰越期間が長いため赤字を無駄にせず、翌期以降の節税につなげられる可能性が高区なります。
マイクロ法人を活用して節税する際の注意点

最後に、マイクロ法人を活用して節税する際の注意点を2つ紹介します。
手続き面での負担が増える
法人の方が個人事業主よりもルールが厳しくやるべきことが多いため、手続き面での負担が増えてしまう点に注意が必要です。
法人ならではの手続きとして、大きく3つ挙げられます。
会社設立
会社設立では以下のように様々な作業を行う必要があります。
・会社概要の決定
・法人用印鑑の作成
・定款の作成および認証(合同会社の場合は定款認証が不要)
・資本金の払込
・法務局での登記申請
また、税務署や年金事務所等への届出等、会社設立後にやるべきことも多数あります。
会社設立時および設立後に必要な手続きに関する詳細は、以下の記事をご覧ください。
社会保険の加入
法人は役員や従業員の人数に関係なく、社会保険の加入が義務付けられています。
社長1人で運営するマイクロ法人も同様です。
社会保険は加入手続きのほか、年に1回「算定基礎届」という届出を行う必要もあります。
個人事業主には社会保険の加入義務がないため、法人ならではの負担といえるでしょう。
決算作業の煩雑化
個人事業主にかかる所得税よりも法人にかかる法人税の方が、仕組みが複雑で会計処理・決算作業の手間が大きいです。
高度な知識が求められる場面も多く、自分ですべて対応するのは容易ではありません。
個人事業主にはないコストがかかる
マイクロ法人を設立・運営する場合、個人事業主には発生しないコストがかかる点も注意が必要です。
法人ならではのコストとして以下の例が挙げられます。
- ・会社の設立費用
- ・法人住民税の均等割
- 資本金や従業員数等、法人の規模に応じてかかる税金で、赤字でも支払いが必要です。
- ・専門家報酬
- 基本的に個人事業主よりも高額になります。
- ・その他経費
- 代表例としてバーチャルオフィス、電話代行サービスが挙げられます。
所得が大きくなれば個人事業主でいるよりもマイクロ法人を設立した方が節税できる可能性が高いと紹介しました。
しかし、マイクロ法人の設立が本当に得になるか否かは、節税効果だけでなく法人ならではの費用も考慮した上で検討が必要です。
法人にかかるコストを考慮せずにいると、法人成りによる節税効果よりも増大する費用負担の方が大きくなってしまう恐れがあります。
まとめ
マイクロ法人は社長1人の会社で、個人事業主の節税目的で設立されます。
個人事業主にかかる所得税は超過累進課税、法人にかかる法人税は税率が一定です。
そのため所得が大きければ法人税の方が税額を抑えられる可能性が高く、マイクロ法人による節税効果が期待できます。
法人の方が経費にできる支出が多く、欠損金の繰越期間が長い点も、マイクロ法人が節税につながる理由です。
ただし、マイクロ法人の設立および運営には手間がかかり、手続き面での負担が増えてしまいます。
また、個人事業主にはかからず法人のみに発生するコストも存在します。
会社設立によって増える手間やコストを考慮した上で、マイクロ法人を設立するか否かの検討が必要です。
マイクロ法人を設立するべきか判断にお悩みであれば、専門家である税理士へご相談ください。
法人・個人事業主の節税対策は
BIZARQにお任せください。
全国オンライン対応・ご相談は無料です。

記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士