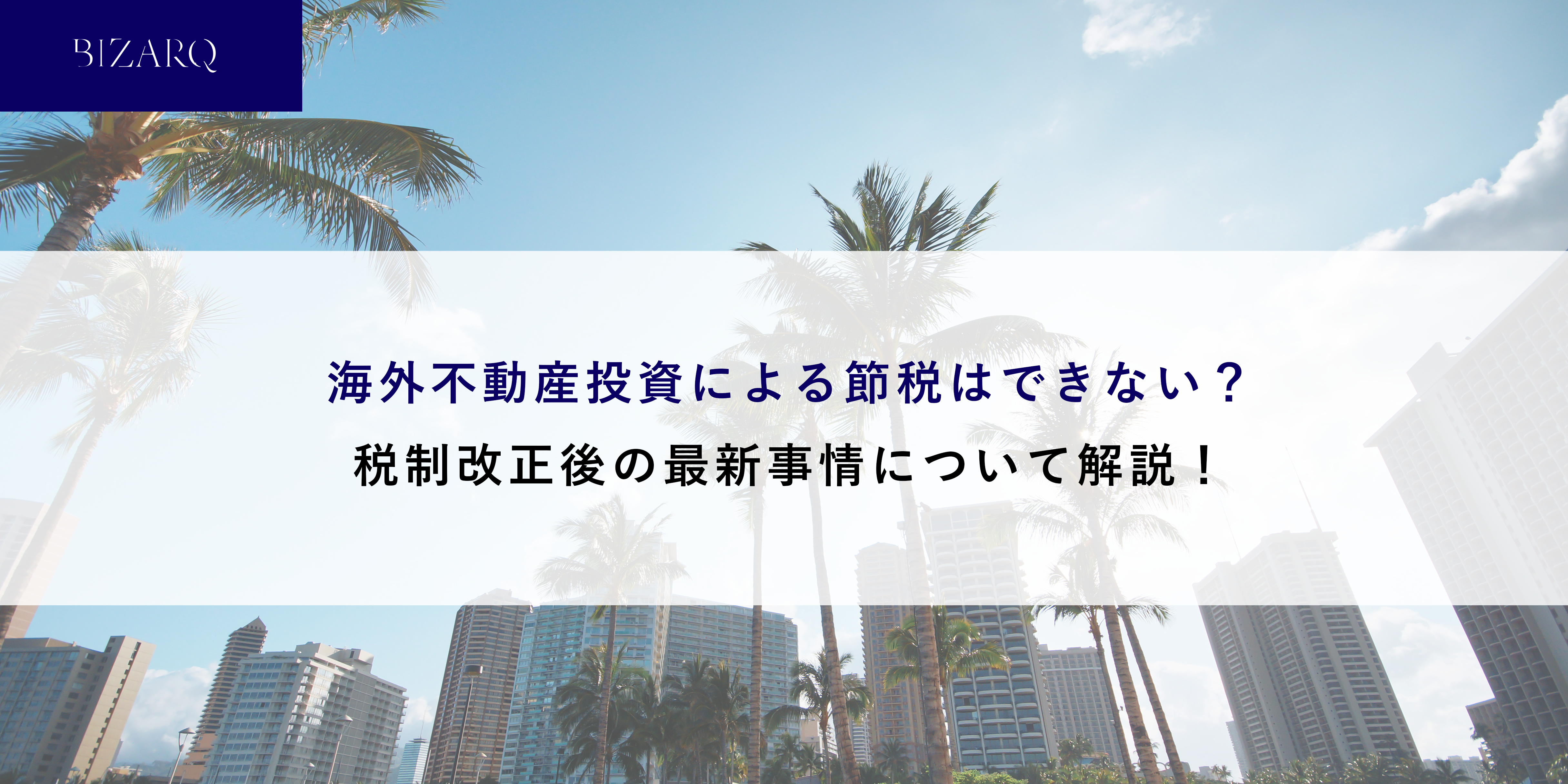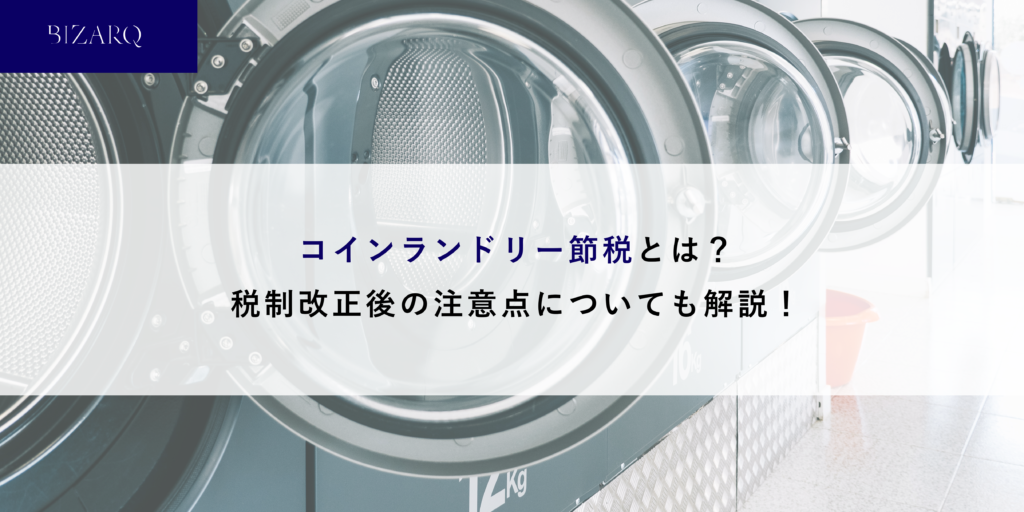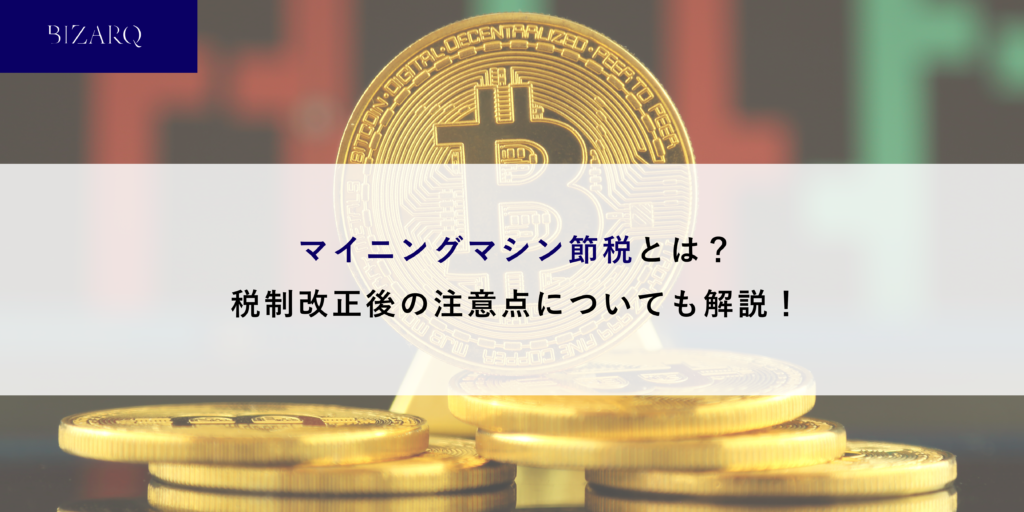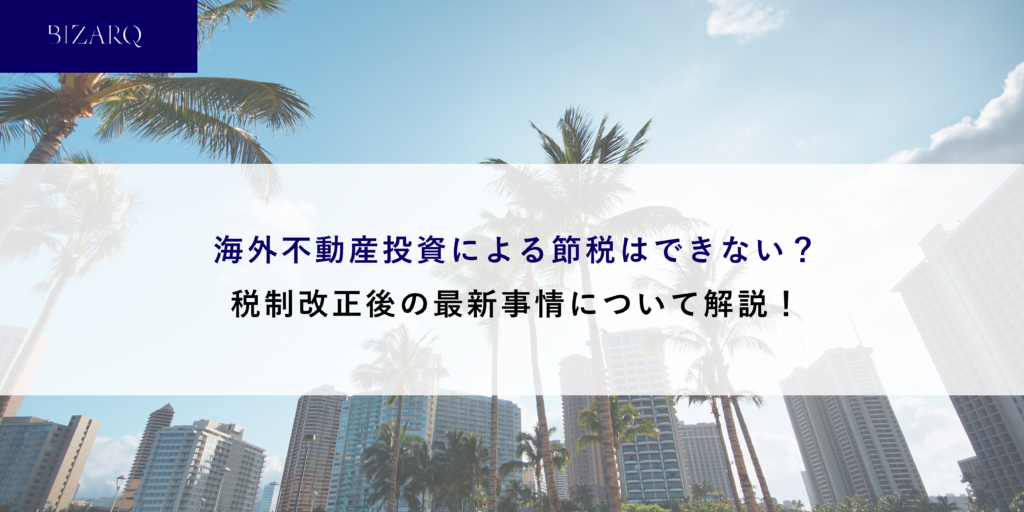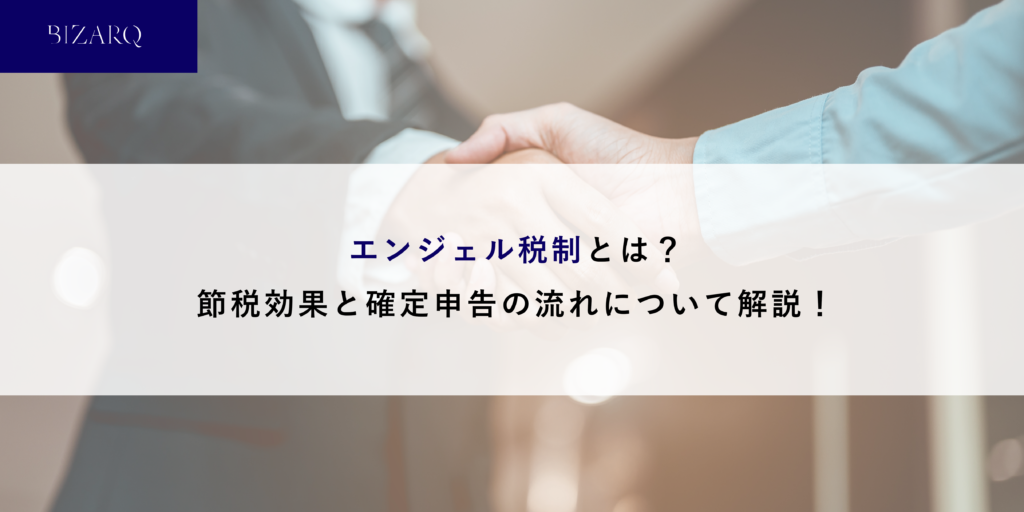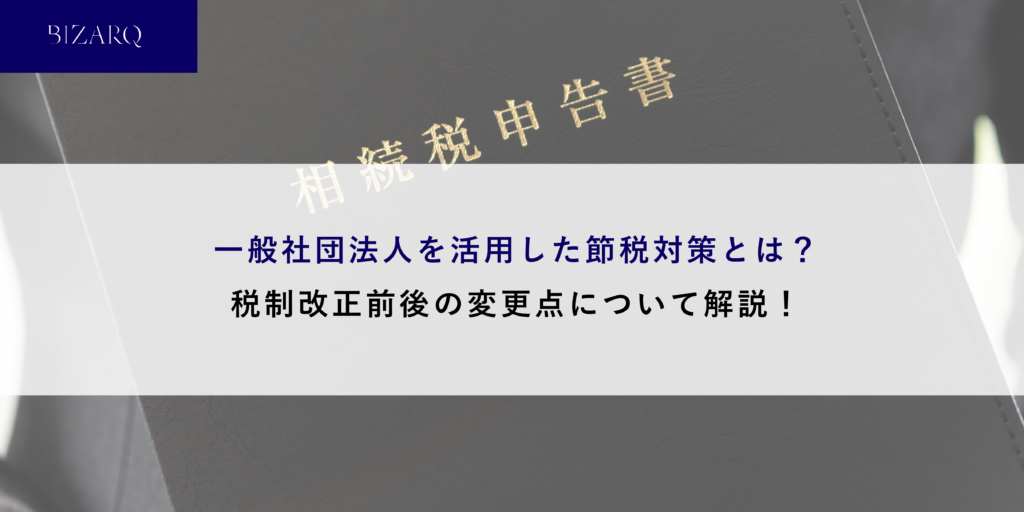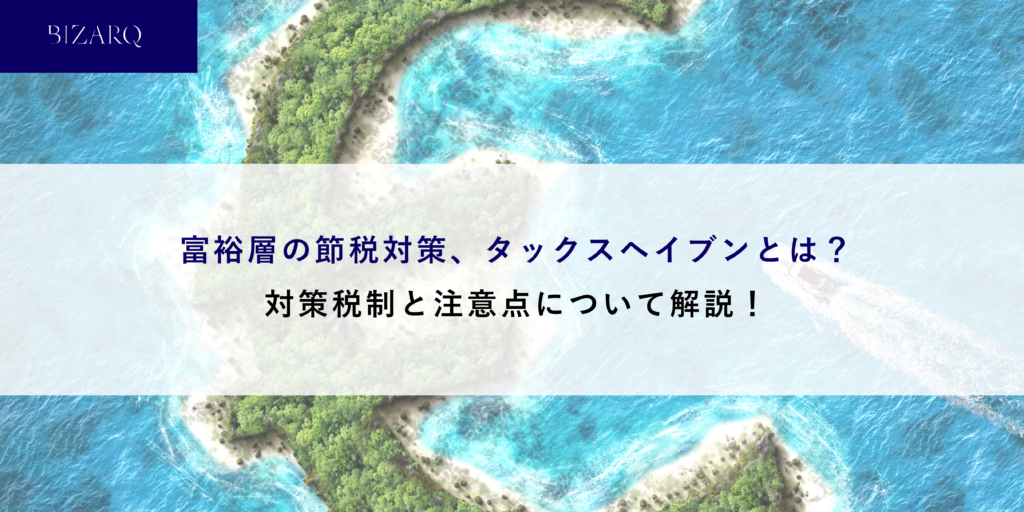
海外不動産による節税対策は、減価償却の仕組みを用いた方法が主流でした。
日本の税制と海外の税制の仕組みを上手く活用することで、一度に高額の減価償却費を計上でき、不動産所得を赤字にする手法がとれたのです。
しかし2020年の税制改正により、海外不動産の償却費相当額を計上した赤字申告ができなくなりました。
海外不動産投資で大きな節税効果を得ることは、実質不可能になった状態です。
節税効果を得られなくなった以上、今後どのような選択肢をとるべきか考える必要があります。
今回は海外不動産投資における節税の最新情報や、海外不動産投資でとれる選択肢について解説します。
国内の不動産投資については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。
CONTENTS
従来の海外不動産投資による節税対策とは

はじめに、従来の海外不動産投資における節税対策について解説します。
従来の節税の仕組み
税制改正前の海外不動産投資では、減価償却の仕組みを用いた節税対策が主流でした。
減価償却とは、固定資産の取得価額を耐用年数に応じて配分し、毎期少しずつ費用計上する会計処理です。不動産のように長期にわたって使用できる資産に用いられます。
減価償却によって計上される費用が減価償却費です。
日本の税制では、耐用年数を超えた中古資産の減価償却では簡便法を利用できます。
簡便法による耐用年数は以下いずれかの方法で算定します。
- 法定耐用年数の全部を経過した資産の場合
- 当該資産の法定耐用年数の20%に相当する年数
- 法定耐用年数の一部を経過した資産
- 法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に、経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
たとえば鉄筋コンクリート造の建物の耐用年数は47年です。
もし50年が経過した鉄筋コンクリート造の建物を購入した場合、簡便法を適用した以下の耐用年数を用いて減価償却を行います。
- 47年×20%=9.4年 端数切捨てで9年
中古の不動産は簡便法を用いた短い耐用年数を用いて減価償却を行うため、一度に計上できる減価償却費が高額になる仕組みです。
海外は日本に比べて建物の寿命が長く、耐用年数も長めに設定されています。
しかし従来の税制では、耐用年数が長い海外の不動産についても日本の所得税法に当てはめて計算ができました。
海外の基準では耐用年数がまだ残っていても、日本の基準では耐用年数を過ぎている物件であれば簡便法を使用できたのです。
計上できる減価償却費がかなり高額になるため、家賃収入を減価償却費が上回るケースも多く、不動産所得を赤字にする手法がとれました。
【参考】海外の不動産事情
日本は新築信仰が強く、中古物件は資産価値が低下しやすい傾向がみられます。
一方、海外は中古物件をリノベーションして住み続ける価値観が一般的な上、そもそも日本に比べて新築物件が多くありません。
そのため、中古物件の需要が高く資産価値も落ちにくいです。
海外はある程度の年数が経過した中古不動産であっても、安定した家賃収入を得られるケースが多いのです。
不動産投資の投資先として特に人気が高かったのはアメリカです。
アメリカは土地が安い分、物件価値のうち建物部分が占める割合が大きくなります。
建物の価値が高い分計上できる減価償却費も高額だったため、節税を目的とした海外不動産投資で高い人気を誇りました。
税制改正による海外不動産の節税封じ込めとは

続いて、税制改正による海外不動産の節税封じ込めについて解説します。
海外不動産の償却費相当額を計上した赤字申告ができなくなった
2020年度の税制改正により、中古の海外不動産から発生する不動産所得が赤字の場合、赤字部分のうち当該不動産の償却費に相当する部分の金額は生じなかったものとみなされるようになりました。
従来の節税対策で行われていた、海外不動産の償却費相当額を計上した赤字申告ができなくなったのです。
中古の海外不動産による家賃収入が300万円、減価償却費が1,000万円、その他経費が200万円の場合を例にします。
税制改正前であれば海外不動産から生じる所得額は以下のようになります。
- 300万円-(1,000万円+200万円)=-900万円
しかし税制改正により、赤字部分のうち償却費に相当する金額はなかったものとみなされるようになりました。
今回の例でいうと、減価償却費1,000万円、不動産所得の赤字が900万円です。
そのため、減価償却費のうち赤字部分の900万円分は生じなかったものとみなされます。
このように、減価償却の仕組みを活用した海外不動産による所得の赤字と日本の他の所得との損益通算ができなくなったため、従来の節税対策は不可能といえます。
法人は従来通りの方法で減価償却費を計上できる
2020年税制改正による海外不動産投資の節税封じ込めは個人を対象としたものです。
法人は税制改正以前と同様に、減価償却の仕組みを用いた海外不動産投資による節税ができます。
そのため、法人を立ち上げて個人が保有している海外不動産を法人へ売却する選択肢も存在します。
ただし、個人が保有している不動産を売却した場合、相手が自身の法人でも売却益に対して譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税が大きいと、法人税の節税分を加味してもかえって税負担が大きくなる恐れもあるため注意が必要です。
今後の海外不動産投資における選択肢
従来のような減価償却の仕組みを活用した節税対策ができない以上、海外不動産投資で節税効果を得るのは難しいのが現状です。
今後、節税目的で海外不動産投資を行うのはおすすめできません。
現在保有している海外不動産についても、保有し続けるメリットがあるか十分に検討する必要があるでしょう。
今後の海外不動産投資における選択肢として2つの例を紹介します。
不動産を売却する
海外不動産を保有し続けても節税効果は期待できないため、不動産を売却するのも1つの選択肢です。
前述のように海外不動産は資産価値が落ちにくいため、築年数が経過した物件でも十分な売却益を得られる可能性があります。
物件によっては購入時より資産価値が上がるケースもみられます。
購入時よりも資産価値が上がっている場合や、安定した家賃収入が期待できない場合に検討する余地があるでしょう。
ただし不動産の保有期間が5年以下の場合、日本では短期譲渡所得とみなされ譲渡益に高い税率が課されます。
譲渡所得税が高額でも今すぐに売却する方法と、税率が下がるまで保有し続ける方法によって発生し得る損失、どちらが大きいか検討しましょう。
家賃収入を得る
海外不動産を手放さない方法です。
海外は築年数の経過による需要の低下が起こりにくい、物件の寿命が長い等の理由から、需要のある物件であれば安定した家賃収入を得られる可能性があります。
節税にはなりませんが、収入が増えるという点で十分にメリットがある方法といえるでしょう。
ただし、すべての海外不動産で安定した家賃収入を得られるとは限りません。
需要の低いエリアの物件や懸念要素のある物件は空室ができやすく、家賃収入が得られない恐れがあります。
当該物件を保有し続ける価値があるか検討する必要があるでしょう。
まとめ
海外不動産投資による節税対策は、減価償却の仕組みを用いた方法でした。
中古の海外不動産は、仕組みを上手く活用すれば計上できる減価償却費がかなり高額になるため、不動産所得を赤字にする手法がとれたのです。
しかし2020年の税制改正により、減価償却の仕組みを活用した海外不動産投資の節税対策は実施できなくなりました。
現在、節税目的で海外不動産投資を行うのはおすすめできません。
今後の海外不動産投資における選択肢として、不動産を売却するか、不動産を保有し続け家賃収入を得る方法が挙げられます。
どちらの方法が良いかはケースによって異なります。
それぞれの方法についてシミュレーションを行い、自身に適した選択肢をとりましょう。
法人・個人事業主の節税対策は
BIZARQにお任せください。
全国オンライン対応・ご相談は無料です。

記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士