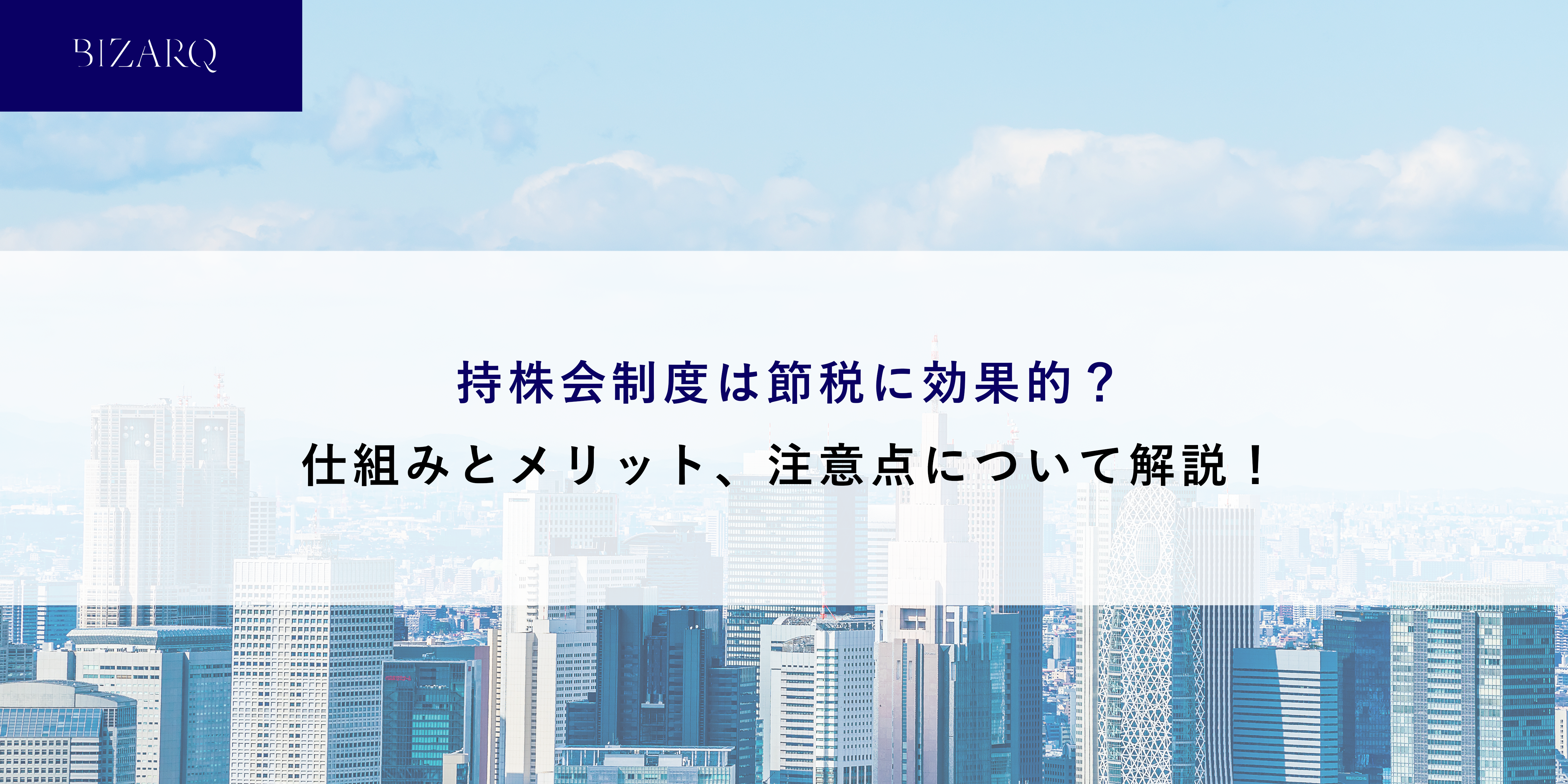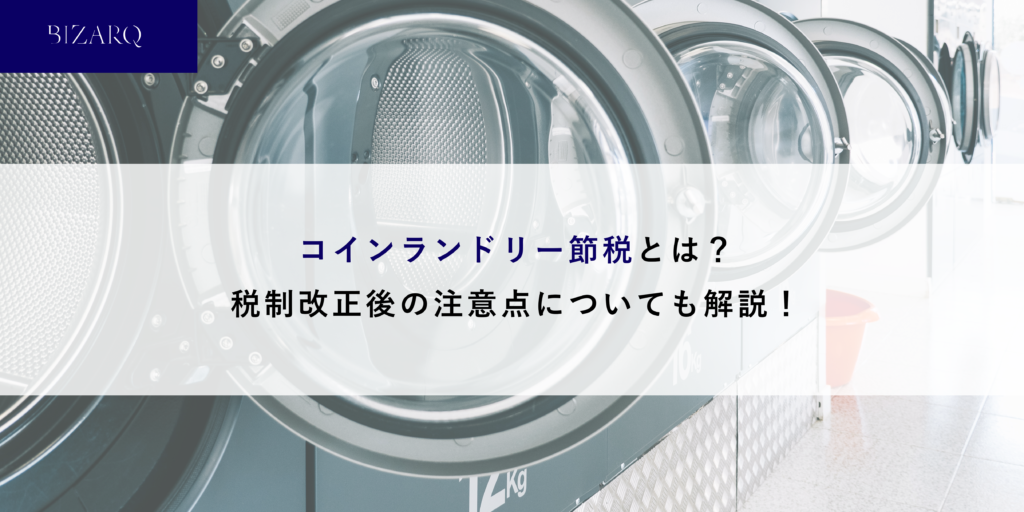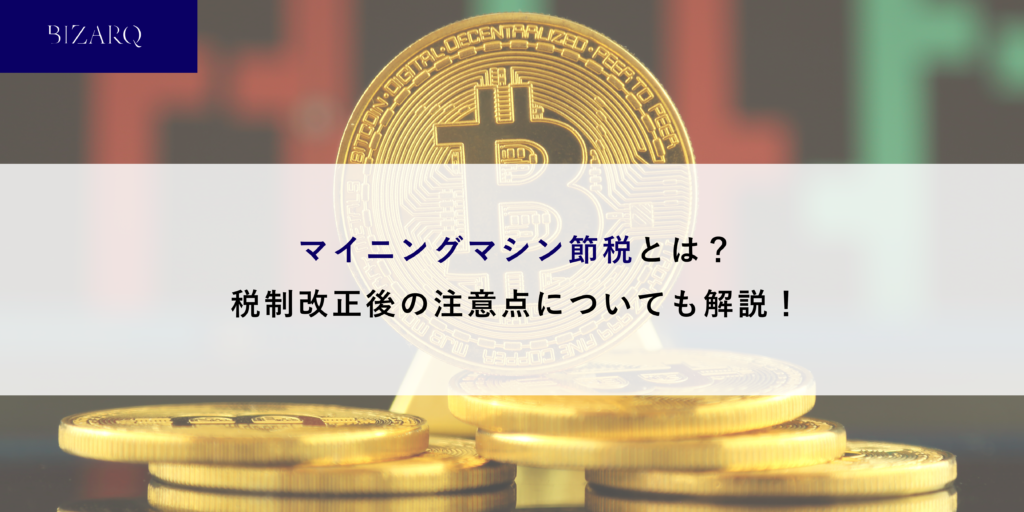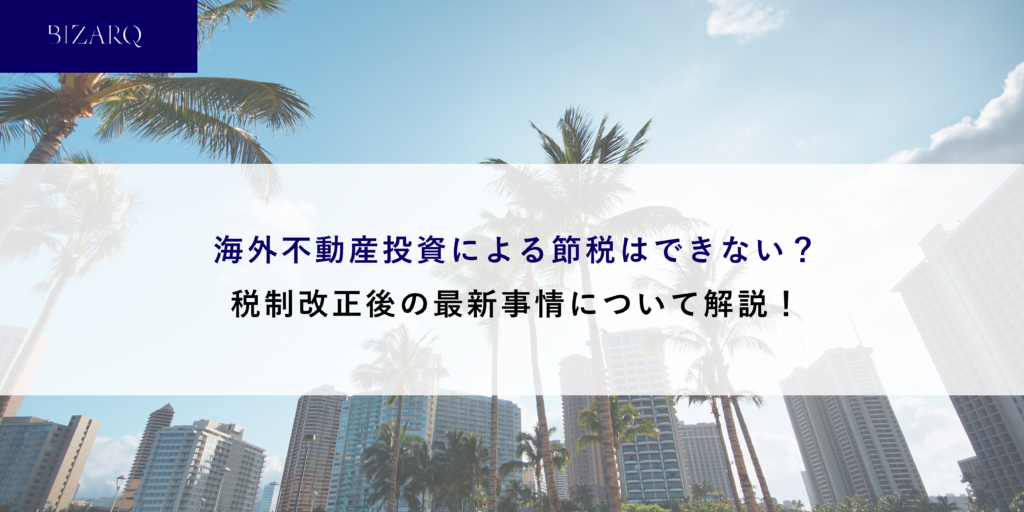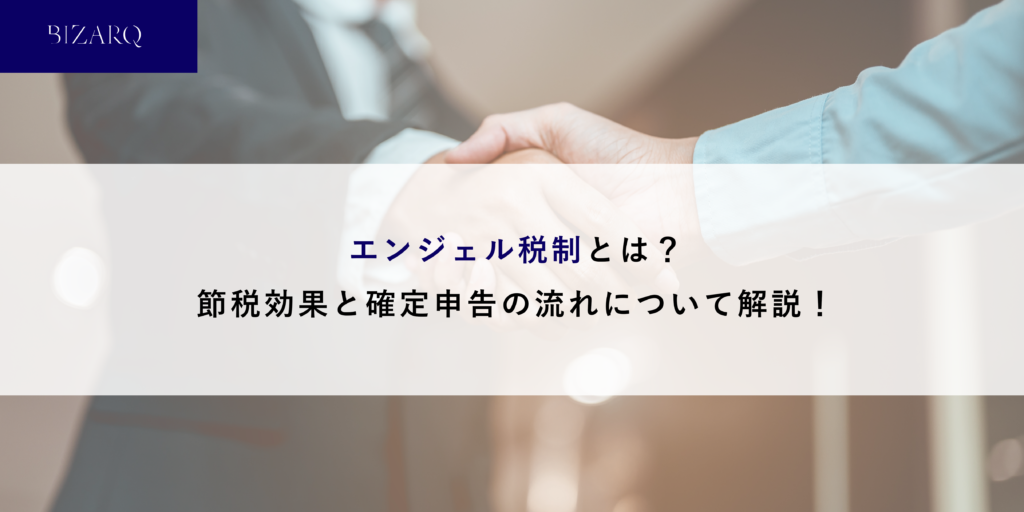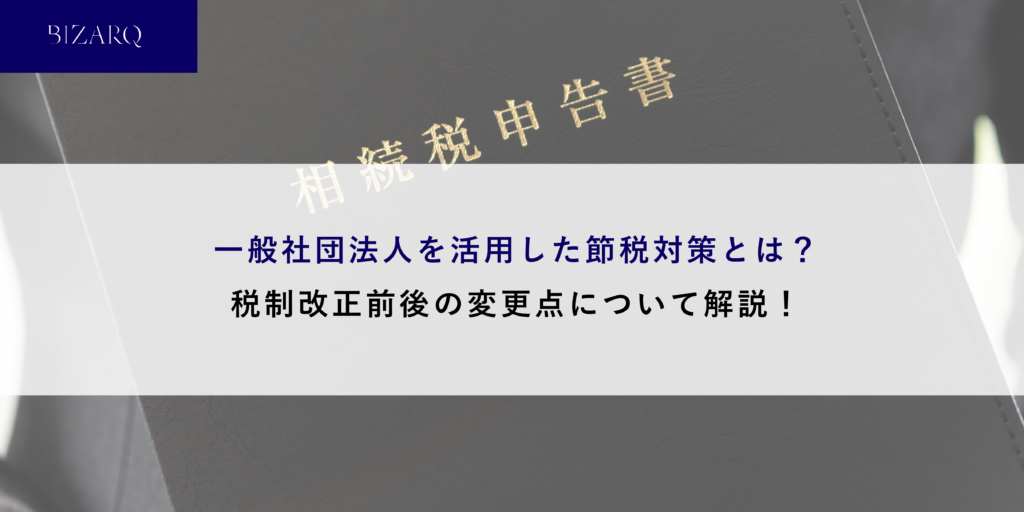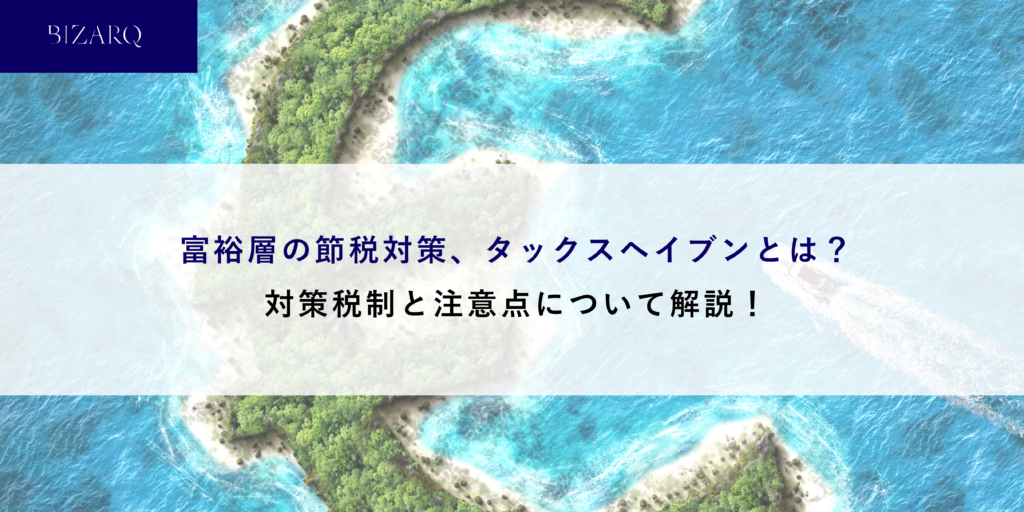
持株会制度は、自社の株式を購入・保有できる制度です。
持株会には様々な種類がありますが、単に持株会と呼ぶ場合は従業員を対象とする従業員持株会を指すケースが多くみられます。
加入者は持株会を通じて自社株を購入し、間接保有する仕組みです。
持株会は経営者・従業員ともに様々なメリットがあります。中でも大きなメリットとして、相続税の節税につながる点が挙げられます。
一方、会社への依存度が高くなる点や、株の買取時にトラブルが起こる恐れがある点に注意が必要です。
今回は持株会制度について詳しく解説します。
一般的な株取引における節税対策については以下の記事で詳しく解説しています。ぜひこちらもご覧ください。
CONTENTS
持株会制度の概要

はじめに、持株会制度の概要を解説します。
持株会制度とは
持株会制度とは、自社の株式を購入・保有できる制度です。同制度を運営する常設機関を持株会と呼びます。
持株会には様々な種類がありますが、単に持株会と呼ぶ場合は従業員を対象とする制度を指すケースが多いです。
持株会を設置している会社であっても、加入するか否かは従業員が自由に判断できます。
以降は特別な記載がない限り、従業員を対象とする持株会を前提に解説します。
持株会制度の仕組み
持株会制度では、加入者から募った出資金を自社株の取得原資に充てます。
出資金を集める方法として、従業員に支払う給与等から一定額の掛金を天引きするのが一般的です。
会員である従業員は、持株会を経由して自社株を購入するイメージです。
各々の出資割合に応じて持分を保有し、持分に応じて配当金を受け取れるようになります。
また、多くの企業では奨励金制度を導入しています。
持株会における奨励金とは、従業員が拠出する掛金に会社が一定額を上乗せする仕組みです。
掛金と奨励金を合算した金額が出資金として扱われるため、拠出分よりも自社株を多く購入できます。
なお、持株会は民法667条に規定される民法上の組合として扱われます。
組合に法人格はないため、持株会は法人税の対象にもなりません。
また、従業員が受け取る配当金は個人の配当所得として扱われ、所得税の対象になります。
持株会に帰属する株式は、会員である従業員が間接保有した状態です。
持分を有しているとはいえ、株式を自由に扱えるわけではありません。詳しくは後述します。
持株会制度のメリット

持株会制度のメリットについて、経営者側・加入者である従業員側それぞれ紹介します。
経営者側のメリット
経営者側の主なメリットとして3つ挙げられます。
相続税の節税につながる
経営者にとっての最も大きなメリットは、相続税の節税につながる点です。
原則として、個人へ株式を譲渡する場合は時価に近い評価額を用いる必要があります。
株式の評価方法に関するルールは相続と贈与によって違いがありますが、会社の財務状態や経営成績等を用いて計算します。
ケースによるため一概にはいえませんが、後継者の税負担が大きくなってしまうケースは珍しくありません。
一方、持株会に株式を譲渡する場合、株式の評価額は配当還元方式で計算した価額となります。
配当還元方式とは、保有株式に応じて受け取る年間の配当金を10%で還元し、元本の株式価額を評価する方法です。
配当還元方式で計算した評価額は通常の評価方法よりも低くなりやすいため、相続税の対象となる相続財産の額を抑えられます。
また、第三者割当増資の場合、オーナーの持株数および純資産は変わらないものの持株割合が下がる仕組みです。
結果として1株あたりの資産額が減少するため、相続財産の額も圧縮されます。
なお、相続税の計算における株式の評価方法には非常に複雑なルールが設定されており、専門知識のない人のみで行うのは容易ではありません。
効果的な節税対策を行うためにも、相続税に関する正確な知識や深い理解が必要です。
制度を活用した節税対策および相続税の計算・申告を正しく行うためには、税務の専門家である税理士へ相談するのが良いでしょう。
構成員の退職や相続による株式の分散が起こらない
持株会の会員である従業員は、持株会を通じて自社株を間接保有している状態です。
しかし、購入した自社株を自由に扱えるわけではありません。自社株の扱いについては規約に従う必要があります。
そのため、規約の中で以下のようなルールを作成すれば、構成員の退職や相続による株式の分散が起きずに済みます。
- ・持株会からの自社株の持ち出しを禁止する
- ・退職する場合は自社株を持株会へ譲渡する
規約の適切な整備は、後述するトラブルを防ぐためにも欠かせません。
なお自社株を安く買い戻せるよう、持株会が自社株を買い取る際の評価方法について配当還元方式と定めるのがおすすめです。
従業員のモチベーションアップが期待できる
持株会に加入すれば、従業員は自社株を安く購入できます。また、配当金やキャピタルゲインの獲得も可能です。
このように従業員にとっても大きなメリットが存在するため、制度を通じて従業員のモチベーションアップも期待できます。
生産性の向上や離職率の低下、さらには採用力の強化にもつながるでしょう。
従業員側のメリット
持株会制度は従業員にもメリットが存在します。そのため、制度の導入によって定着率や従業員満足度の向上が期待できるでしょう。
従業員側のメリットを3つ紹介します。
少額で株を購入できる
上場企業の株取引は100株単位(1単元)と定められています。
そのため、通常の方法で株を購入するためにはまとまった資金が必要です。
一方、持株会制度に加入すれば毎月一定の掛金を拠出することで自社株を購入できます。
小額でも株を購入できる点は、従業員にとっての大きなメリットといえるでしょう。
配当金やキャピタルゲインを得られる
持株会を通じて株を購入すれば、株式数に応じて配当金やキャピタルゲインを得られます。
持株会に長く加入し株の購入を続けるほど保有株式数も増えていき、配当金等も高額になっていきます。
奨励金分の利益を得られる
持株会を実施する企業のうち、奨励金制度を導入している企業は非常に多いです。
たとえ株による利益が横ばいだとしても、奨励金がある以上は最低でも奨励金分の利益は得られます。
奨励金制度があれば従業員が損をするリスクは低く、高確率でプラスになるといえるでしょう。
持株会制度の注意点

最後に、持株会制度を導入する上での注意点を3つ紹介します。
会社への依存度が高くなる
持株会制度を導入すると、会員である従業員が会社に依存してしまう恐れがあります。
自社株の価格は一般的に会社の業績に連動する仕組みであり、会社の業績が落ちれば株価も下落する恐れがあります。
会社の業績が下落し自社株の価値が下がれば、持株会の会員である従業員の保有資産も目減りしてしまいます。
持株会加入者の保有資産は、会社による影響を直接的に受けるのです。
一般的に、従業員の主な収入源は会社から支給される給与や賞与であるため、持株会に加入することで収入と資産の両方について同じ会社に依存する状態になってしまいます。
買取時にトラブルが起こる恐れがある
持株会の会員である従業員が退職する場合、退職者の保有する自社株は会社が買い取るのが一般的です。
そして、株式をいくらで買い取るかについて従業員とトラブルになる恐れがあります。
自社株の買い取りがスムーズに進まない・購入価額が高くなってしまうといった事態のほか、退職する従業員との関係が悪化するケースも有り得ます。
自社株買取時のトラブルを防ぐためには、規約の中で買い取り価格について明記が必要です。
実体のない持株会は否認されるリスクがある
持株会制度を相続税の節税対策に活用できるのは事実です。
しかし、節税対策のみを目的に実体のない持株会制度を設けてしまうと、対象の持株会について否認される恐れがあります。
実態がないとして否認されてしまえば、配当還元方式を活用した相続税の節税対策ができません。
相続税の節税対策は、持株会制度を適切に運用した際の副産物ととらえるべきです。
従業員が自由に加入できる状態にする・配当を出す・規定を整える等、会社の機関としてしっかり運営しましょう。
まとめ
持株会に加入すると、加入者である従業員の給与等から掛金が天引きされ、拠出した掛金は自社株の購入に充てられます。
従業員は各々の出資割合に応じて持分を保有し、配当金を受け取れるようになります。
持株会は経営者側と従業員側の両方にメリットがある制度です。
特に相続税の節税につながる点は、経営者側の最も大きなメリットといえるでしょう。
ただし、持株会には注意点も存在します。
メリットを最大限に享受するためには、注意点について事前に把握した上で的確な対策を行う必要があります。
今回紹介した内容を押さえ、制度を上手く活用しましょう。
法人・個人事業主の節税対策は
BIZARQにお任せください。
全国オンライン対応・ご相談は無料です。

記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士