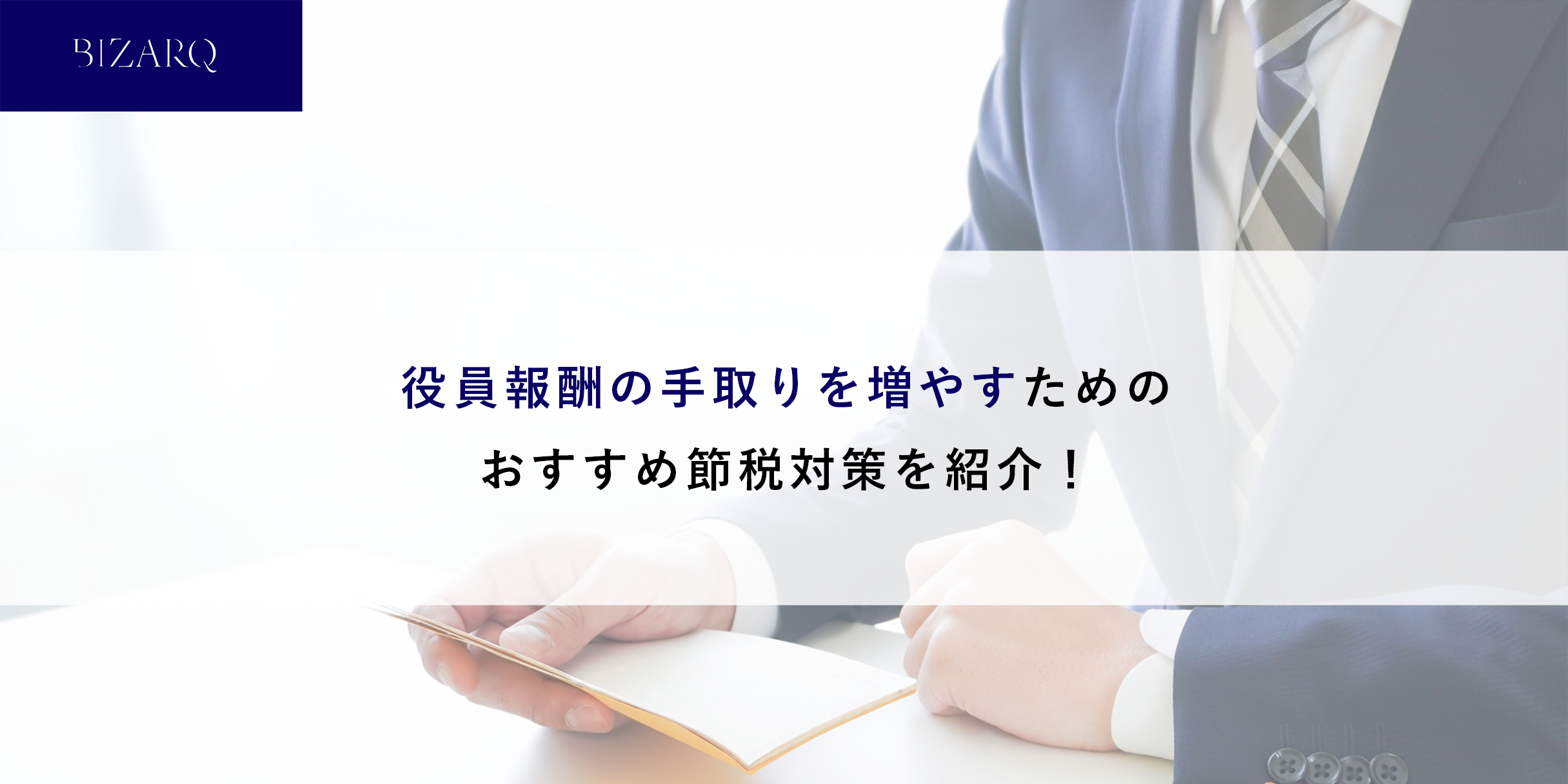会社から支払われる役員報酬は給与所得に該当し、所得税の対象となります。
単純に役員報酬の金額を増やしても、差し引かれる所得税額も大きくなるため、結果として手取りはそれほど増えないケースが多くみられます。
役員の手取りを増やすためには、役員報酬の金額そのものを上げるだけでなく、節税テクニックの活用も必要です。
今回は役員報酬の手取りを増やすためのおすすめ節税対策を紹介します。
所得税の負担を最小限に抑えるためには、所得税そのものに関する理解も大切です。
以下の記事で所得税の仕組みを詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。
CONTENTS
役員報酬の節税対策について見る前に

役員報酬の手取りを増やすための節税対策について見る前に、まずは役員報酬の概要を解説します。
役員報酬と通常の給与の違い
役員報酬とは、会社などの法人から役員に対して支払われる報酬です。
所属する法人から支払われる点は通常の給与と同じですが、役員報酬と給与にはさまざまな違いがあります。
損金算入の要件
給与はすべて損金に算入できますが、役員報酬は損金算入できるものが以下の3種類に限られます。
- 定期同額給与
- 1ヶ月以下の一定期間ごとに同じ金額が支給される役員報酬です。
- 税務署への届出が必要であり、届出に記載の額を超えた支給分は損金不算入となります。
- 事前確定届出給与
- 事前に税務署へ支払日・支払額の届出が必要な報酬であり、役員に対する賞与のようなイメージです。
- 届出書の内容と実際の支給日や支給額に少しでも相違があると、該当の会計期間に支給した事前確定届出給与すべてが損金不算入になります。
- 業績連動給与
- 会社の利益に連動して金額が決まる役員報酬です。
- 業績連動給与および非同族会社の完全子会社である同族会社のみ支給が認められています。
法的なルールの厳しさ
前述のように、役員報酬は損金算入できるものに規定があります。
届出の必要性や損金不算入になってしまうケースなど、通常の給与よりも法的なルールが厳しく定められています。
使用する勘定科目
通常の給与で使用する勘定科目には、「給与」「給与賃金」「給与手当」などがあります。
一方で、役員報酬に使用する勘定科目は「役員報酬」と定められています。
役員報酬にかかる税金とは
役員報酬による収入は所得に該当するため、所得税および住民税の課税対象です。
前項で紹介したように、役員報酬は従業員へ支払う一般的な給与とは異なる扱いを受けます。
しかし、所得の区分としては通常の給与と同じく給与所得に該当します。
給与と役員報酬は会社法において明確に区別されていますが、所得税法では同じように扱われます。
所得額の計算方法についても、一般的な給与所得と同じです。
役員報酬の手取りを増やすための節税対策4選

役員報酬の概要を理解したところで、続いて役員報酬の手取りを増やすための具体的な方法を4つ紹介します。
通勤手当を支給する
手取り額を増やす効果的な方法のひとつに、通勤手当の支給が挙げられます。
通勤手当は通勤に際して公共交通機関やマイカーなどを利用する人を対象に、交通費の支給・補填を目的として支給する手当です。
役員・従業員を問わず、要件を満たしていれば通勤手当の支給ができます。
通勤手当は原則として非課税であり、源泉徴収票に記載される支払金額にも含まれません。
そのため、支給総額が同じであっても、一部を通勤手当として支給すれば、所得税額が少なくなり結果として手取りが大きくなります。
現時点で通勤手当を支給していないのであれば、通勤手当の制度を導入・支給するのがおすすめです。
しかし、通勤手当は上限なく支給できるわけではありません。
あくまでも交通費として妥当で合理的な金額に限られます。
役員社宅制度を活用する
役員社宅制度の活用も、役員の手取りを増やす方法として効果的です。
役員が個人名義で契約している物件を会社名義に変更することで、該当の物件が社宅扱いになります。
賃貸物件の契約を会社名義にすると、会社が家賃を支払う物件を役員や従業員に貸し出すイメージになります。
そして、会社から支給する給与や報酬額から賃料に相当する金額を控除します。
役員報酬の金額が賃料相当額の分減ることで課税対象額も少なくなるため、所得税・住民税の節税につながるのです。
なお、賃料相当額は住宅の面積を基に算出されます。
面積が広い・相場をはるかに超える高額な家賃などの豪華な住宅は社宅として認められないため注意が必要です。
役員社宅制度については国税庁の公式サイトで詳しく案内されているため、そちらもご覧ください。
配偶者や親族を役員にする
役員の配偶者や親族を役員にすることで、結果的に役員の手取りを増やせる可能性もあります。
所得税は所得額が大きいほど適用される税率が高くなる累進課税です。
そのため、個人年収と世帯年収が同じ金額であっても所得税額の合計額が同じとは限りません。
個人年収1,000万円の場合と、夫婦それぞれの年収が500万円で世帯年収1,000万円である場合、世帯年収1,000万円の方がトータルの所得税は少なくなります。
世帯の一人が高額な収入を得るよりも、同世帯の中で収入を分散した方が所得税を抑えられるのです。
自身の役員報酬100万円であったのを、自身の役員報酬80万円・配偶者の役員報酬20万円に変更した場合を例にします。
自分の役員報酬は少なくなりますが、減額となった分は配偶者に役員報酬として支給されるため、世帯として受け取る収入に変化はなく、且つ個人に課せられる高額な所得税を回避できます。よって、世帯トータルの手取りは大きくなります。
適用対象となる控除制度を漏れなく活用する
所得税の負担を最小限に抑えるため、適用対象となる控除制度を漏れなく活用しましょう。
所得控除とは、特定の要件を満たすことで所得から一定額を控除できる制度です。
所得税の金額は所得控除適用後の課税所得額をもとに計算するため、所得控除の金額が高いほど所得税は低くなります。
所得控除には基礎控除や給与所得控除のように自動的に適用されるものだけでなく、自己申告が必要なものもあります。
せっかく適用要件を満たしていても、自己申告をしなかったために適用を受けられず税負担が重くなるケースは珍しくありません。
適用対象となる所得控除をすべて活用するためには、所得控除についての理解と、適用対象となる控除制度の確認が必要です。
見逃しやすい所得控除の具体例を6つ紹介します。
医療費控除
自分や、自分と生計を一にする配偶者・親族のために支出した医療費が一定額を超える場合に利用できる制度です。
診療費のほか、入院費・医薬品の購入費なども対象となります。
セルフメディケーション税制
医療機関での処方せんではなく、ドラッグストアなどで自身が選択・購入した医薬品の合計が一定額を超える場合に利用できる控除制度です。
医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方の適用しか受けられません。
両方の要件を満たしている場合は、より有利な方を選びましょう。
なお、医療費控除およびセルフメディケーション税制は、いずれも適用のためには確定申告を行う必要があります。
生命保険料控除
生命保険料や個人年金保険料の支出がある場合に利用できる制度です。
会社の年末調整でも適用を受けられます。
地震保険料控除
地震保険料の支出がある場合に利用できる制度です。
生命保険料控除と同じく会社の年末調整でも適用できるため、控除のために確定申告を行う必要はありません。
配偶者控除
所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に適用できる制度です。
納税者本人の所得によって控除額が異なります。
扶養控除
配偶者以外の控除対象扶養親族がいる場合に利用できる制度です。
まとめ
所得税は所得が増えるほど税率も上がる仕組みです。
そのため、役員報酬を増やしても額面が増えたのと同じ分手取り額が増えるわけではありません。
役員の手取りを増やしたい場合、役員報酬の単純な増額ではなく、別の方法を検討する必要もあるでしょう。
今回紹介した節税対策は、いずれも簡単で大きな効果が期待できる方法です。
それぞれのポイントや得られる効果を押さえつつ、自身に適した節税対策を行いましょう。
法人・個人事業主の節税対策は
BIZARQにお任せください。
全国オンライン対応・ご相談は無料です。

記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士