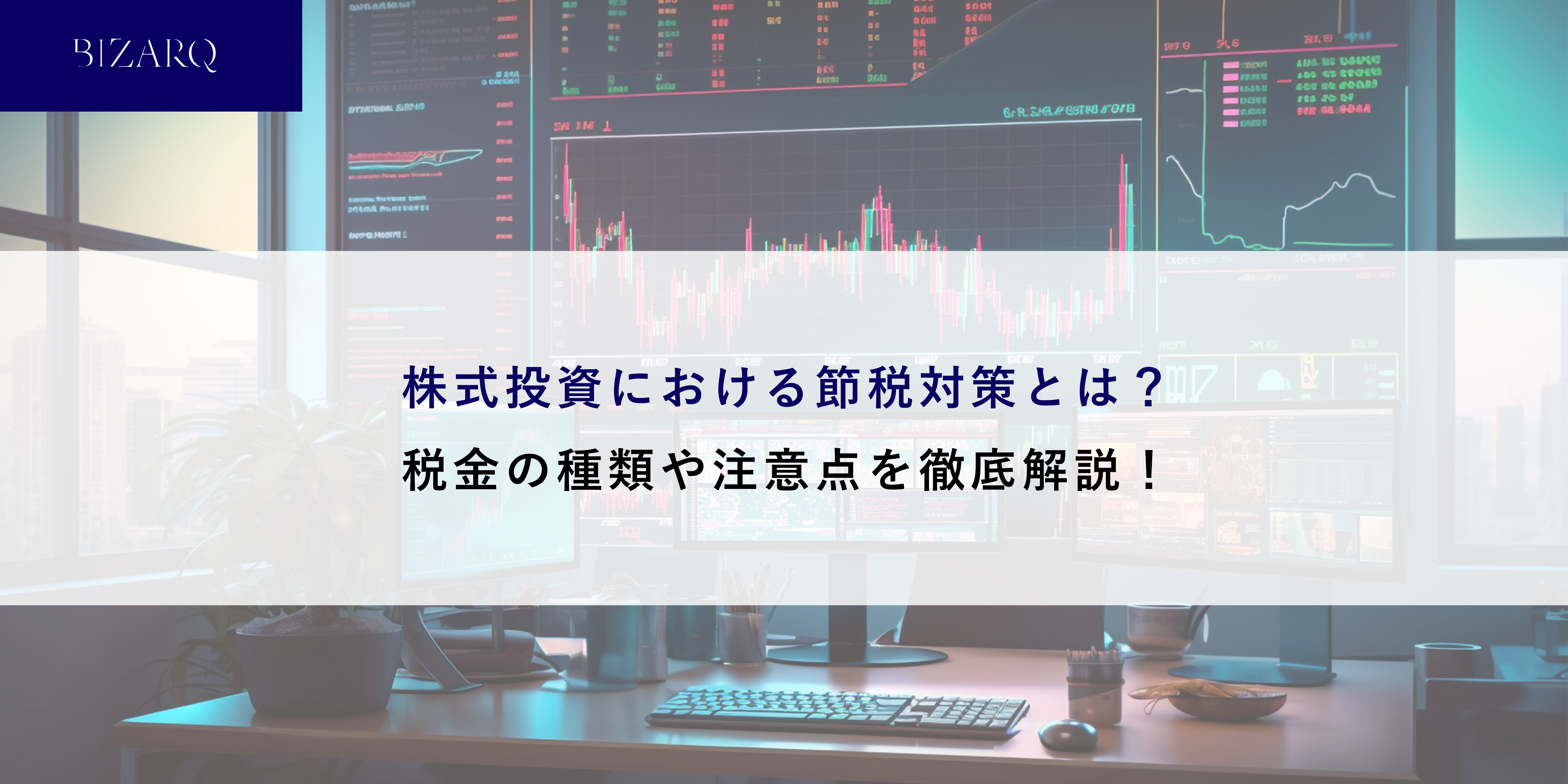株式投資に関係のある所得として、配当所得と譲渡所得が挙げられます。
配当所得は株の配当があった場合に、譲渡所得は株式売買で利益が出た場合に発生します。
所得の発生要因や金額に関係なく、所得税の仕組みを理解した上で正しい方法を行えば、所得税の節税が可能です。
株式投資に関しても節税対策として効果的な手段が複数存在します。
今回は株取引で発生する所得の扱いや、株式投資における節税対策について詳しく解説します。
投資に関する節税対策については他の記事でも詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。
CONTENTS
節税について見る前に|株式投資で発生する所得とは

株式投資で発生する所得として以下の2種類が挙げられます。
- ・配当所得
- ・譲渡所得
株式投資でややこしいのが、所得の種類によって計算方法や確定申告での扱い方が異なる点です。
株式投資によって発生した利益がどちらの所得に該当するか正しく理解しなければ、確定申告および税額の計算を誤ってしまう恐れがあります。
そのため、株式投資を行う際は節税対策以上に株式投資で発生する所得についての理解が重要です。
株式投資で発生する所得について詳しく解説します。
株式の配当・利子等|配当所得
株式の配当および利子等は配当所得の対象です。
配当所得の金額は以下の計算式で算出します。
源泉徴収税額差引前の収入額-株式等の取得を目的とした借入金の利子=配当所得
また、株式の配当や利子等は源泉徴収の対象であり、口座に入金されるのは源泉徴収後の金額です。
源泉徴収で適用される税率は、該当の株式が上場会社のものか否かによって異なります。
- ・上場株式等の配当や利子等:20.315%
- 所得税および復興特別所得税が15.315%、地方税が5%です。
- ・上場株式等以外の利子等:20.42%
- 地方税は課せられません。
上場株式等の配当等は、確定申告の方法として以下3つの選択肢があります。
- 申告不要
- 少額配当の要件を満たすものや上場株式等の配当等および投資法人からの金銭の分配は、確定申告不要制度の対象となります。
- 総合課税での確定申告
- 各種所得の金額を合計して所得税額を計算する方法です。
- 原則として配当控除の適用対象となります。
- 申告分離課税での確定申告
- 配当控除の適用対象外になりますが、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能です。
株式売買による利益:譲渡所得
株式売買によって利益が出た場合の所得は譲渡所得と呼ばれます。
譲渡所得とは、資産の売却によって発生する所得の総称です。
株式に限らず、土地や建物といった不動産や、ゴルフ会員権などを譲渡した際にも発生します。
株式等にかかる譲渡所得等の金額は以下の計算式で求めます。
譲渡による総収入金額-必要経費=譲渡所得等の金額
株式売買による譲渡所得に課せられる税率は、上場株式・一般株式ともに20.315%です。
税率の内訳は、所得税が15%・地方税が5%・復興特別所得税が0.315%となります。
株取引で確定申告が不要となるケース
原則として、株取引で利益があれば確定申告が必要です。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は確定申告が不要となります。
上場株式等の配当等について「申告不要」を選んでいる
前述したように、配当等は源泉徴収された後の額が入金されます。
そして「申告不要」を選んでいる場合は確定申告の必要がありません。
申告不要以外を選んでいる・源泉徴収された分の還付を受けたい等の場合は確定申告が必要です。
株取引を「特定口座(源泉徴収あり)」で行っている
株式売却による譲渡益が発生していても、株取引を「特定口座(源泉徴収あり)」で行っている場合は確定申告が不要となります。
給与収入が2,000万円以下であり、かつ、株取引による利益と給与以外の収入の合計額が年間20万円以下である
給与所得者は勤務先で年末調整を受けるため、多くの人は確定申告が不要です。
給与所得者で確定申告が必要な人として、給与収入が2,000万円を超える人や、給与以外の収入が20万円を超える人が挙げられます。
株取引による利益がある場合でも、給与収入が2,000万円以下であり、かつ、株の利益を含めた給与以外の収入が20万円以下であれば確定申告が不要です。
また、株取引で損失が出ている場合は税金が発生し得ないため、確定申告をしなくても問題ありません。
ただし、所得税の還付を受けるためには確定申告を行う必要があります。
株取引の節税テクニック3選

株取引に関する税金を抑えるためのテクニックを3つ紹介します。
株取引による利益を年間20万円以下に抑える
主に給与所得者が活用しやすいテクニックです。
前章で、給与収入が2,000万円以下かつ株取引による利益と給与以外の収入の合計額が年間20万円以下である場合は確定申告が不要と紹介しました。
確定申告が不要とは、すなわち所得税が発生しないということです。
給与収入が2,000万円以下で他の収入がない場合、株取引による利益を20万円以下に抑える方法は、効果的かつ確実な節税対策といえます。
大前提として、株取引の利益として計上されるのは、売却によって実現した分のみです。
仮に2021年に30万円で購入した株式Aが2022年末時点で50万円になった場合、売却すれば20万円の譲渡益が発生します。
しかし、売却せずに保有し続けたままでいれば、利益が実現せず課税対象にもなりません。
売却しておらず実現していない利益のことを含み益、売却によって実現した利益を実現益と呼びます。
このように含み益が貯まった状態でも、年末時点での実現益が20万円以下の場合は、あえて売却せず実現益を20万円以下に抑えれば課税対象になりません。
逆に実現益が既に20万円を超えていても、含み損のある株式を年内に売却してトータルの利益を20万円以下に抑えられるケースもあります。
なお、株取引による利益が年間20万円以下であっても、給与を除くその他の収入との合計が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
副業による収入や家賃収入などがある場合は注意しましょう。
売却損と配当金を相殺する
株式の売却による損失と配当等による配当所得の両方がある場合、売却損と配当金の相殺が可能です。
たとえば、2023年の配当等による収入が30万円、株式売却による損失が15万円とします。
この場合、所得税の課税対象になるのは30万円-15万円=15万円です。
配当等は源泉徴収された後の額が入金されるため、30万円に対してすでに所得税が控除された状態になっています。
したがって、今回の例では確定申告を行うことで、損失である15万円部分にかかる源泉徴収税額の還付を受けられます。
還付を受けるには確定申告が必須であるため、株式売却による損失がある場合は必ず確定申告を行いましょう。
NISAやiDeCoで投資を行う
投資運用の方法として、株取引ではなくNISAやiDeCoを選ぶのもひとつの選択肢です。
NISAはNISA口座内で購入した金融商品について、一定期間、一定の投資枠内で発生した利益が非課税となる制度です。
すでに紹介したように、譲渡益と配当金はともに20%を超える所得税が課せられます。
NISAでは譲渡益・配当金どちらも非課税になるため、通常の方法による投資よりも手に入る利益が大きくなる仕組みです。
NISAと似た制度として、つみたてNISAというものがあります。
NISAよりも非課税期間が長い一方で、非課税投資枠の上限が低くなっています。
NISAとつみたてNISAはどちらか一方しか実施できないため、違いを押さえた上で自分に合う方を選ぶことが大切です。
つみたてNISAについては以下の記事で詳しく解説しています。
iDeCoは個人で積み上げる年金制度です。
毎月一定の掛金を支払って積み立てていき、掛金は預金や投資信託等に運用されます。
発生した運用益は非課税であるため、NISAと同様に税負担なく投資運用ができる仕組みです。
iDeCoについては以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
株式投資では配当所得と譲渡所得という2つの所得が発生し、それぞれ扱いや税率が異なります。
株取引に関する確定申告を正しく行うためには、所得の種類や違い、必要な手続きについて深い理解が必要です。
所得に対する正しい理解が、結果として効果的かつ正しい節税対策につながります。
今回、株式投資に関する節税テクニックを3つ紹介しました。
いずれも大きな節税効果が期待できる方法ですが、実施する上で知識が必要な部分や、ちょっとした手間が発生する部分が存在します。
株式投資の節税について疑問や不安があれば、専門家である税理士にご相談ください。
法人・個人事業主の節税対策は
BIZARQにお任せください。
全国オンライン対応・ご相談は無料です。

記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士