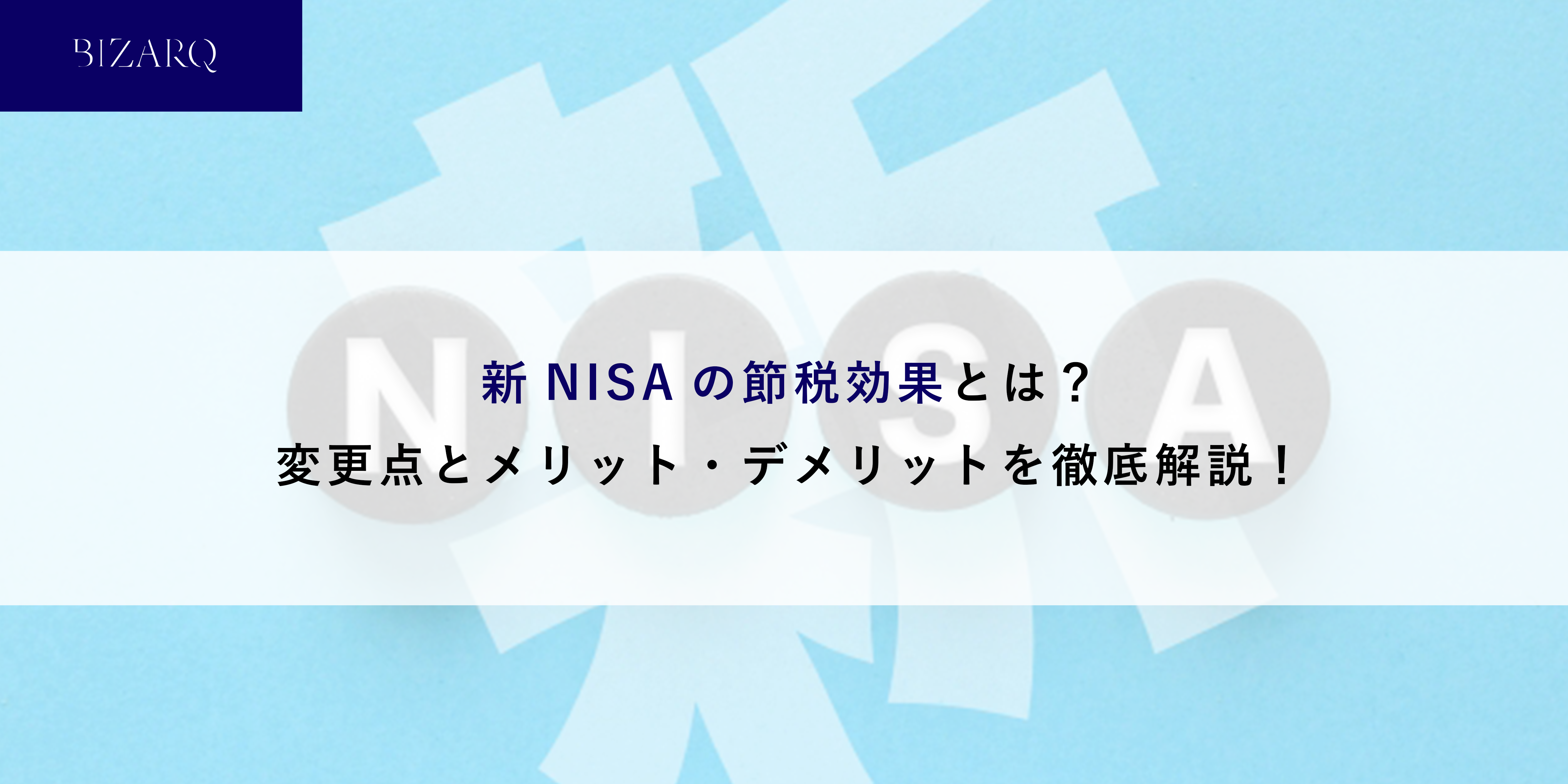NISAとは、2014年1月に開始された非課税で投資ができる制度です。
NISA口座で発生した運用益は所得税の対象にならないため、通常の投資のような負担がかかりません。
そんなNISAですが、2024年1月から制度が改正され、新たなNISAが始まりました。
2024年1月以降に開始されたNISAが新NISAと呼ばれています。
従来のNISAと新NISAでは様々な点に相違があるため、改めて新NISAに対する理解が必要です。
今回は新NISAの変更点やメリット・デメリット、どれほどの節税効果を得られるかについて解説します。
NISAと比較される場面が多い投資制度として、iDeCoが挙げられます。iDeCoについては以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。
※本記事では便宜上、2023年12月までのNISAを旧NISA、2024年1月に開始されたNISAを新NISAと表現します。
CONTENTS
新NISAとは

新NISAとは、2024年1月から開始されたNISA制度の通称です。
現在新たに開始できるNISA制度はいわゆる新NISAの方であり、2023年12月以前までのNISA制度の利用はできません。
口座開設および旧NISA制度を適用した買い付けもできなくなっています。
新NISAの変更点

この章では、2023年12月までのNISAと新NISAの違いを紹介します。
投資枠の種類と併用可否
旧NISAと新NISAの大きな違いの1つが、投資枠の種類および枠の併用可否です。
新NISAには、つみたて投資枠と成長投資枠という2種類の投資枠が存在します。
つみたて投資枠の年間投資枠は120万円、成長投資枠は240万円です。
つみたて投資枠の投資対象商品はつみたてNISAと同じであり、年間投資枠は成長枠に比べて低めに設定されています。
つみたて投資枠は旧制度におけるつみたてNISAに近い仕組みといえるでしょう。
旧NISAにも一般NISAとつみたてNISAという2種類の投資枠が存在しましたが、併用は不可能でした。
たとえば一般NISAを利用している人の場合、新たにつみたてNISAを開始することはできなかったのです。
一方、新NISAはつみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能です。2種類の投資枠の併用によって、最大で年360万円まで投資できます。
口座開設期間
旧NISAの口座開設期間は、つみたてNISAが2042年末まで、一般NISAが2023年末までと設定されていました。
一方、新NISAは口座開設期間の定めがありません。各々の好きなタイミングで自由に口座を開設できます。
なお、NISA口座は成人(18歳以上)で開設可能です。
非課税保有期間
新NISAの非課税保有期間は、投資枠2種類とも無期限です。
つまり、保有期間が何年であってもNISAによって発生した運用益は非課税のままとなります。
旧NISAの非課税保有期間は、一般NISAが5年間、つみたてNISAが最大20年間でした。
非課税保有期間の無期限化は、新NISAの大きなメリットといえるでしょう。
非課税保有限度額
旧NISAの非課税保有限度額は、一般NISAが600万円、つみたてNISAが800万円です。
前述の通り投資枠の併用ができないため、非課税保有限度額の最大は実質としてつみたてNISAの800万円でした。
新NISAの非課税保有限度額は、つみたて投資枠と成長投資枠の合計で1,800万円です。
ただし、成長投資枠の非課税保有限度額は1,200万円と設定されています。
たとえば、つみたて投資枠だけで1,800万円の保有は可能ですが、成長投資枠だけで1,800万円の保有はできません。
購入できる商品
新NISAで購入できる商品は投資枠の種類によって異なります。
新NISAのつみたて投資枠で購入できる商品は、長期の積立分散投資に適した一定の投資信託です。旧制度におけるつみたてNISAの対象商品と同じものとなります。
成長投資枠で購入できる商品として、上場株式や投資信託などが挙げられます。
ただし、以下に該当する商品は対象外です。
- ・整理・管理銘柄
- ・信託期間20年未満、高レバレッジ型及び毎月分配型の投資信託等
新NISAによる節税効果

新NISAによってどれほどの節税効果を得られるのか、特定口座と新NISA口座で同条件の投資を行った際の税額をシミュレーションして比較しましょう。
今回使用する条件は以下の通りです。
- ・月の投資額は10万円
- ・積立前の元金は0円
- ・積立期間は10年
- ・年利5%で運用
- ・特定口座の場合に運用部分にかかる税率は、所得税・住民税・復興特別所得税あわせて20.315%
- ・配当金は考えない
- ・最終積立金額の差を比較する
まずは新NISAの場合です。金融庁が公開しているNISAの資産運用シミュレーションを利用しました。
1年目・5年目・10年目の運用収益と、最終積立金額は以下の通りです。
- ・1年目の運用収益:2.8万円
- ・5年目の運用収益:80.1万円
- ・10年目の運用収益:352.8万円
- ・最終積立金額:15,528,228円
続いて特定口座で投資した場合のシミュレーション結果を紹介します。こちらはカシオ計算機株式会社が公開している積立計算(複利毎課税)ツールを利用しました。
1年目・5年目・10年目の税引後利息と、最終積立金額は以下の通りです。
- ・1年目の税引後利息:25,996円
- ・5年目の税引後利息:638,135円
- ・10年目の税引後利息:2,708,328円
- ・最終積立金額:14,708,328円
通常の投資の場合は運用収益が課税対象のため、手元に残るお金は少なくなります。
そのため全くの同条件で投資をした場合、NISAの方が最終積立金額が高くなるのです。
今回のシミュレーション結果の比較からも、新NISAには節税効果があると断言できるでしょう。
新NISAのメリット

この章では新NISAのメリットを3つ紹介します。
旧NISAよりも大きな節税効果を得られる可能性がある
新NISAの大きなメリットが、旧NISAよりも大きな節税効果を得られる可能性がある点です。
前提として、NISA口座で行った投資は普通分配金と譲渡益が非課税になります。この仕組みは旧NISAも同じです。
新NISAは旧NISAよりも年間投資枠および非課税保有限度額が大きいため、非課税で運用できる額が大きくなります。
したがって、運用額によっては旧NISAよりも大きな節税効果が期待できるのです。
非課税期間が無期限のため、より長期投資がしやすくなった点もメリットといえるでしょう。
旧NISAは投資枠の上限が低く、そもそも少額からの長期投資が前提だったため、大きな額の投資運用はできませんでした。
非課税保有限度額は買い付け残高で管理される
新NISAの非課税保有限度額は、買い付け残高で管理されます。
たとえば100万円の買い付けをし、投資商品が150万円に値上がりしたとしても、生涯投資枠の残りは1,700万円のままです。
また、金融商品を売却すれば投資枠が復活します。
500万の買い付けをして残り枠1,300万円の人が金融商品200万円を売却すれば、投資枠は200万円+1,300万円=1,500万円になります。
旧NISA制度では口座内の商品を売却しても再利用ができなかったため、この変更点も大きなメリットです。
好きなタイミングでの現金化が可能
好きなタイミングでの現金化が可能な点も、新NISAの大きなメリットです。
NISA口座から資金を引き出すタイミングに定めはありません。
NISAと比較される場面が多いiDeCoは引き出しができるのが原則60歳からです。
好きなタイミングで売却や引き出しができ現金化がしやすい点は、NISAならではのメリットといえます。
新NISAのデメリット
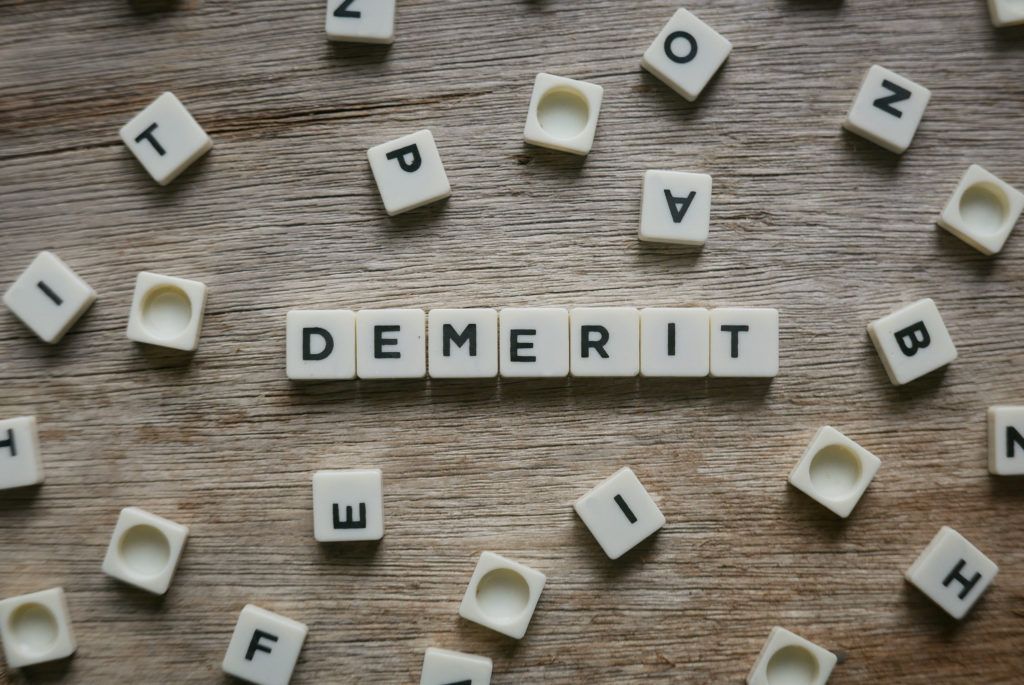
続いて、新NISAのデメリットを2つ紹介します。
買い付け額が所得控除の対象になるわけではない
新NISAはあくまでも、運用によって発生した配当金と譲渡益が非課税になる制度です。
比較される場面の多いiDeCoのように、投資した額が所得控除の対象になるわけではありません。
NISAは税負担なく投資できる制度であって、投資行為そのものが節税につながる制度ではない点を押さえる必要があります。
損益通算の仕組みは存在しない
NISAには損益通算の仕組みが存在しません。
投資における損益通算とは、ある取引で発生した損失を、別の取引で発生した利益と相殺できる仕組みです。
投資による損失が発生すれば別の取引で発生した利益と相殺でき、最終的な利益が小さくなるため、税負担も下がります。
しかし、NISAには損益通算の仕組みがありません。
そもそも損益通算はトータルの利益部分のみを課税対象とするための仕組みです。
NISAは運用益が非課税のため、損益通算を可能とする理由がないといえます。
損益通算は投資で重要な概念の1つだからこそ、NISAでは適用されない点に注意が必要です。
NISAで出た損失を一般口座や特定口座と損益通算することもできません。
NISAは一定の基準を満たした商品のみが対象ではあるものの、必ずしも利益が出るとは限らない、つまり損失発生のリスクが存在する点にも注意する必要があるでしょう。
まとめ
2024年1月に開始された新NISAは、旧NISAと比較して様々な変更点がみられます。
大きな違いとして、投資枠の種類・併用の可否・上限額が挙げられます。
口座開設期間および非課税保有期間が無期限になった点も大きな違いでしょう。
旧NISAと新NISAには多くの違いがあるため、今後新たにNISAを始めようと考える人は、必ず新NISAのルールを確認しましょう。
新NISAには大きなメリットが複数ありますが、デメリットも存在します。
資産運用は必ずしも利益が出るとは限らず、自己責任による部分も大きいです。
新NISAのルールやメリット・デメリットをしっかり押さえた上で、新NISAを利用するか判断しましょう。
法人・個人事業主の節税対策は
BIZARQにお任せください。
全国オンライン対応・ご相談は無料です。

記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士