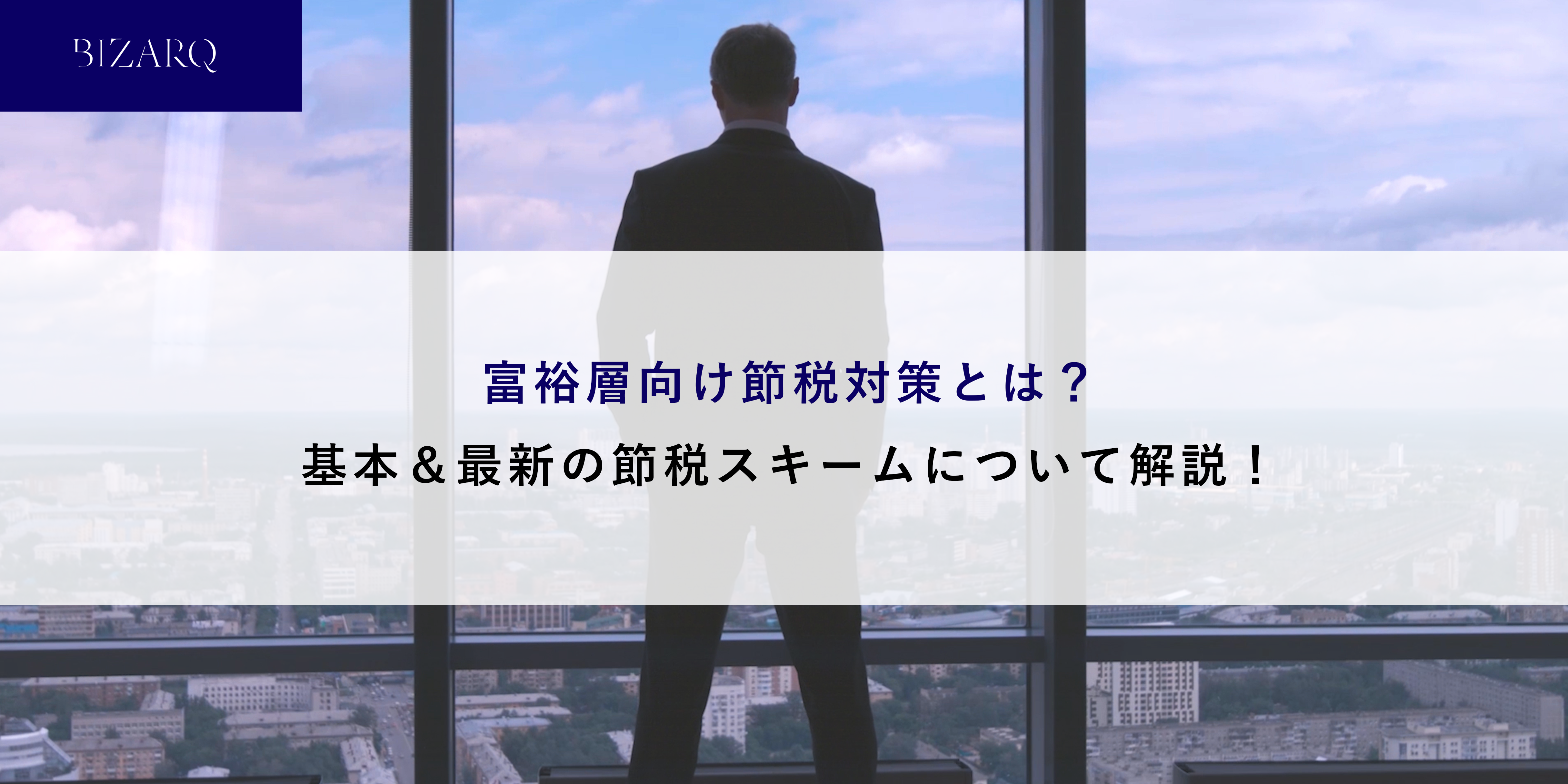富裕層は所得額や財産価額といった課税対象金額が高額なため、税額も高くなります。
所得税は所得額が大きくなるにつれて税額が高くなる累進課税制度を採用しています。
相続税は基礎控除額の枠が大きいですが、富裕層のように保有財産が多い場合は控除しきれないケースが多くみられます。
結果として、納税者である相続人の税負担が大きくなります。
富裕層は所得税および相続税の節税対策が欠かせないといえるでしょう。
今回は富裕層向け節税対策について、基本的な事項と最新の節税スキームの両方を紹介します。
高所得者の節税対策については以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。
CONTENTS
富裕層向け節税対策 所得税編

この章では、富裕層向けの所得税節税対策を4つ紹介します。
各種控除制度を最大限に活用する
所得税を最小限に抑えるため、各種控除制度を最大限に活用することが大切です。
所得税には所得控除と税額控除という2つの控除制度があります。
所得控除は、所得額から引くことで課税対象となる所得額を減額する制度です。
税額控除は、課税対象所得に税率を乗じて算出した税額から直接差し引きます。
所得控除と税額控除はそれぞれ適用要件が設定されていますが、要件を満たせば自動で適用されるわけではありません。年末調整や確定申告での手続きが必要です。
控除制度の要件を満たしていても手続きをせずにいては控除を受けられず、必要以上に税金を払う結果になってしまいます。
税額を最小限に抑えるため、適用対象となる控除制度の有無を必ず確認しましょう。
また、生命保険料控除や寄附金控除など、納税者自身がある程度支出額を決められる制度も存在します。
富裕層で金銭的に余裕がある場合、生命保険料の額を増やす・寄附を多く行う等、控除制度を活用するために意識して行動するのもおすすめです。
資産運用を行う
資産運用も富裕層におすすめの節税対策です。
株式売買によって発生する所得は譲渡所得に該当します。譲渡所得で損失が出た場合は他の所得との損益通算が可能なため、節税につながります。
利益が出た場合、トータルの税額が増えるものの、現預金をそのまま持っているだけより資産額も増えるため、結果プラスとなります。
また、2024年1月から開始された新NISAもおすすめです。
新NISAは2023年12月までのNISAに比べて非課税投資額が大きい上、非課税保有期間が無期限に設定されています。
通常の投資と違い運用益に課税されないため、税負担を抑えながら資産運用が可能です。
税負担なく投資ができる制度として、iDeCoも挙げられます。
iDeCoは掛金として支出した額がそのまま所得控除の対象になるため、NISAよりも節税効果が大きいです。
iDeCoについては以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
資産管理会社を活用する
資産管理会社とは、名前の通り資産の所有や管理運用を目的とした会社です。
資産を多く保有している富裕層の方は、資産管理会社の活用によって大きく2つのメリットが期待できます。
1つ目は、収益の分散ができることです。
不動産や配当のある株式等から得る収益は、資産の保有者が個人の場合はすべて個人の者になります。一方、保有者が会社であれば会社のものです。
そして、自身の家族や親族を資産管理会社の役員等にして会社から役員報酬を支払えば、資産から発生する収益を分散する形になります。
資産にかかる収益が1人に集中して所得税の負担が大きくなるのを防げます。
2つ目は、所得にかかる税額を抑えられることです。
資産管理会社を活用すれば、資産から得られる収益は会社の所得となります。
所得が一定を超えると所得税率よりも法人税率の方が低くなり、所得額が同じでも会社の方が税額を抑えられます。
そのため、保有資産が多い場合資産管理会社を活用して法人として資産の管理運用を行う方が節税につながるのです。
不動産投資を行う
不動産投資・不動産運用が所得税の節税につながるのは、不動産所得の赤字は損益通算が可能なためです。
「資産運用を行う」で紹介した譲渡所得と同様、不動産所得で出た赤字を他の所得と相殺すれば、課税対象所得を抑えられます。
不動産投資は以下の理由から赤字になりやすいため、損益通算を狙いやすいともいえます。
- ・不動産関連の支出は経費にできる
- ・減価償却費を計上できる
なお、不動産投資は所得税だけでなく相続税の節税にも効果的な方法です。
詳しくは次章で解説します。
富裕層向け節税対策 相続税編

続いて、富裕層向け相続税の節税対策を4つ紹介します。
生前贈与を行う
生前贈与とは、文字通り存命中に行う贈与です。
生前贈与という呼び方をする場合は相続税の節税を目的とした行為を指し、通常の贈与とは区別するのが一般的です。
生前贈与によって相続税の対象となる財産価額を減らすことで、相続税の節税につながります。
生前贈与の方法として、主に以下の4つが挙げられます。
- 暦年贈与
- 年間の贈与額が110万円以下(贈与税の基礎控除額以下)の場合に贈与税がかからない仕組みを活用した生前贈与です。
- 1年で贈与できる額には限りがありますが、早いうちから毎年生前贈与をすればトータルで高額の財産移転ができます。
- 住宅取得等資金の贈与
- 直系尊属から受けた住宅取得等資金の贈与のうち一定額が非課税になる制度を活用した節税対策です。
- 教育資金の一括贈与
- 所定の手続きを行った上で行われた直系尊属からの教育資金の一括贈与は、最大1,500万円まで非課税になります。
- 事前に金融機関での手続きが必要かつ要件がやや複雑なため、制度に対する深い理解が必要です。
- 結婚・子育て資金の一括贈与
- 「教育資金の一括贈与」と同じく、金融機関で所定の手続きを行う必要があります。
生命保険等を活用する
生命保険料の非課税枠を活用した相続税の節税対策です。
生命保険の加入者である被保険者が亡くなった場合、保険金受取人に保険金が支払われます。
死亡保険金は被保険者である被相続人の財産ではないものの、みなし相続財産として相続税の計算対象に含まれます。
しかし、死亡保険金は「500万円 × 法定相続人数」が非課税枠として設定されているため、全額が相続税の対象になるわけではありません。
生命保険の活用により、相続税の負担を抑える効果が期待できます。
なお、死亡保険料の受取人は法定相続人以外にも設定可能です。
生命保険の活用は単に節税対策として有用なだけでなく、資産分散の効果も得られます。
不動産を購入する
不動産投資は、所得税と相続税両方の節税につながる方法です。
不動産投資が相続税の節税につながる理由として、不動産価値の評価方法が挙げられます。
相続税の課税対象となる遺産総額を計算する際に用いる不動産評価額は、一般的に購入価額や時価よりも2~3割ほど下がります。
つまり、同額の現金をそのまま有しているよりも不動産を購入した方が、かかった金額は同じでも遺産総額が少なくなるのです。
不動産投資による節税については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
事業承継を行う
事業承継とは、経営者の事業や会社を後継者に引き継ぐ行為です。
事業承継によって後継者が引き継ぐ自社株式や事業用資産には、贈与税や相続税が課されます。
一見すると事業承継は相続税の節税どころか、税負担を重くする行為に移るかもしれません。
しかし、事業承継には特例措置が設けられており、一定の要件を満たすことで課税対象となる株式や納付猶予割合の拡充を受けられます。
この仕組みが、事業承継税制です。
事業承継税制を活用すれば税負担を抑えられるため、将来的に事業承継を検討しているのであれば、早いうちから準備を始めるのが良いでしょう。
まとめ
富裕層は所得額や相続税の対象となる財産価額が高額なため、税負担が重くなるケースが多くみられます。
そのため、税負担を抑えるための節税対策が必須です。
節税対策をするか否か、そもそも知っているかどうかで税額が大きく変わるケースは珍しくありません。
今回、富裕層向けの所得税・相続税の節税対策を紹介しました。
課税の仕組みや節税スキームに対する理解を深め、効果的な節税対策を実施しましょう。
法人・個人事業主の節税対策は
BIZARQにお任せください。
全国オンライン対応・ご相談は無料です。

記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士