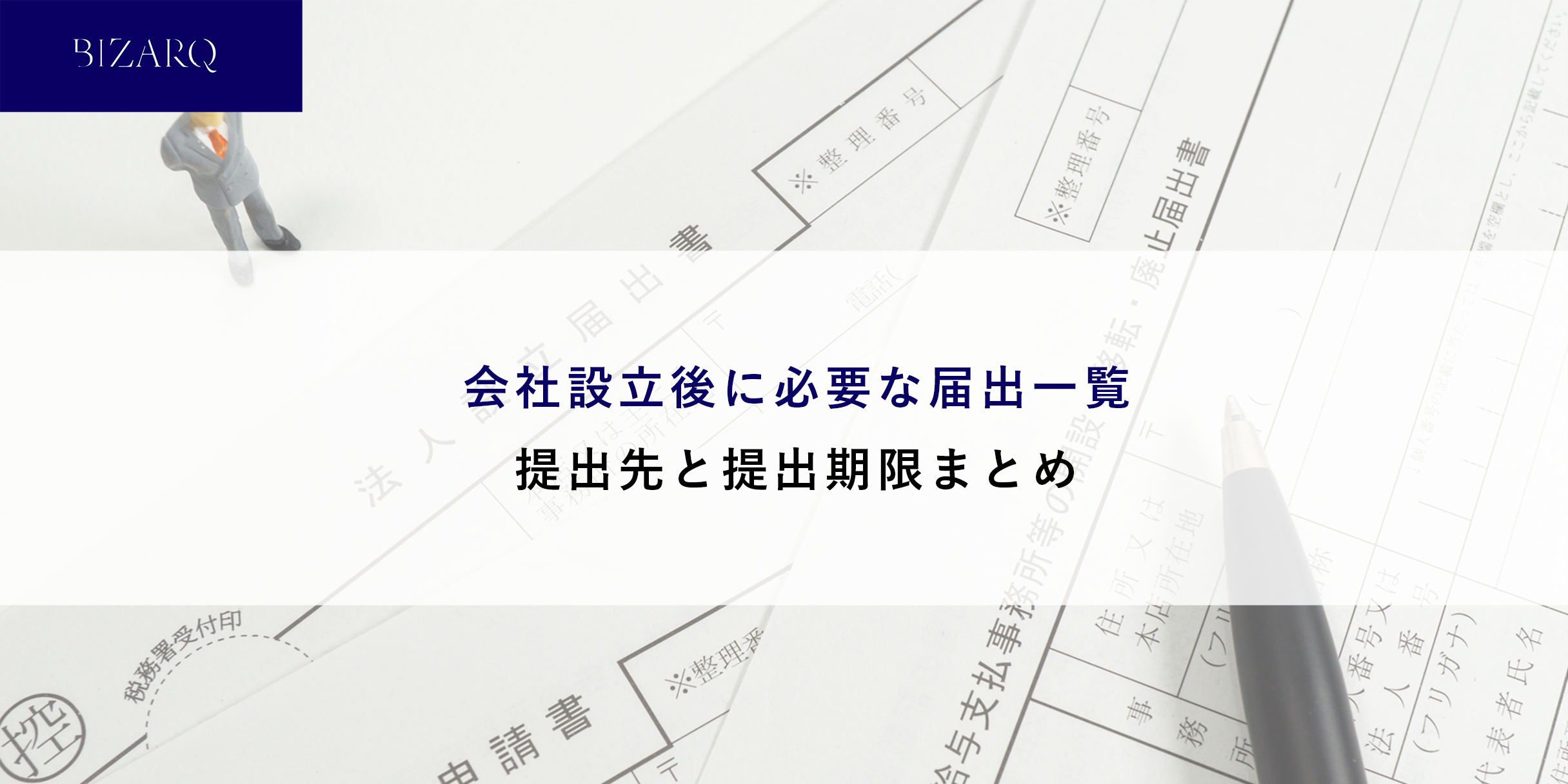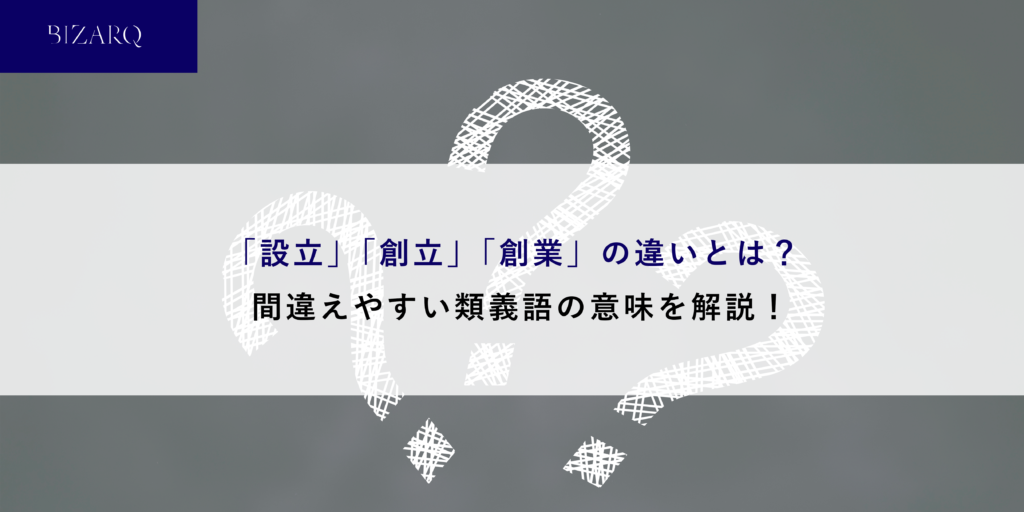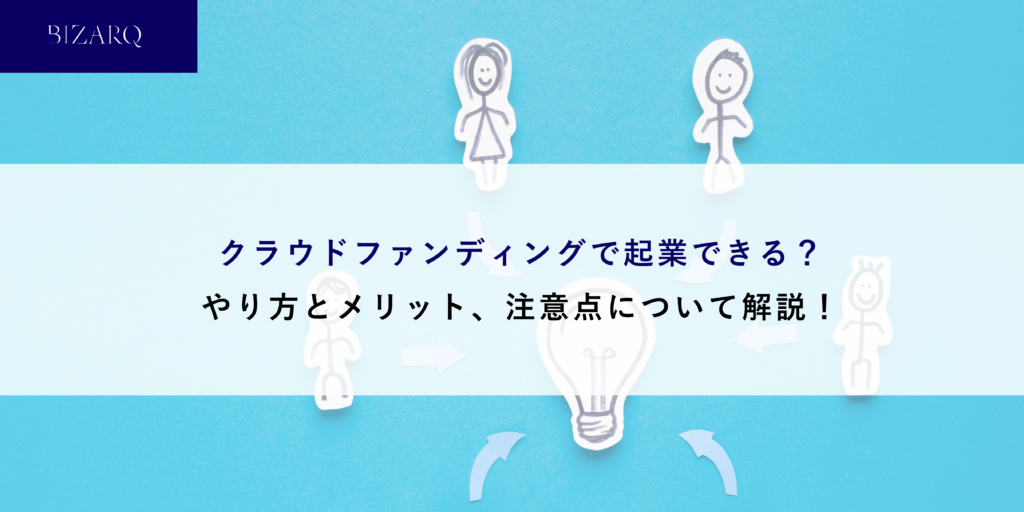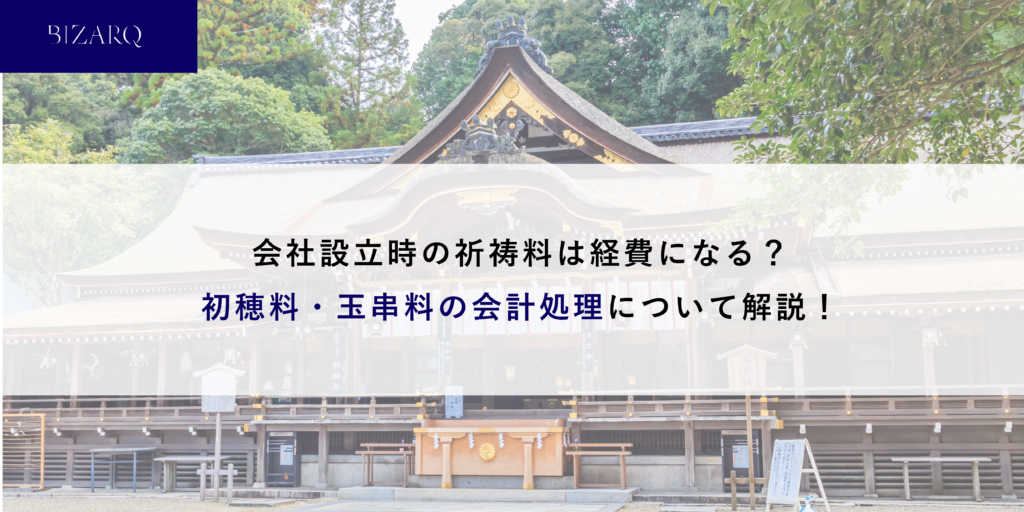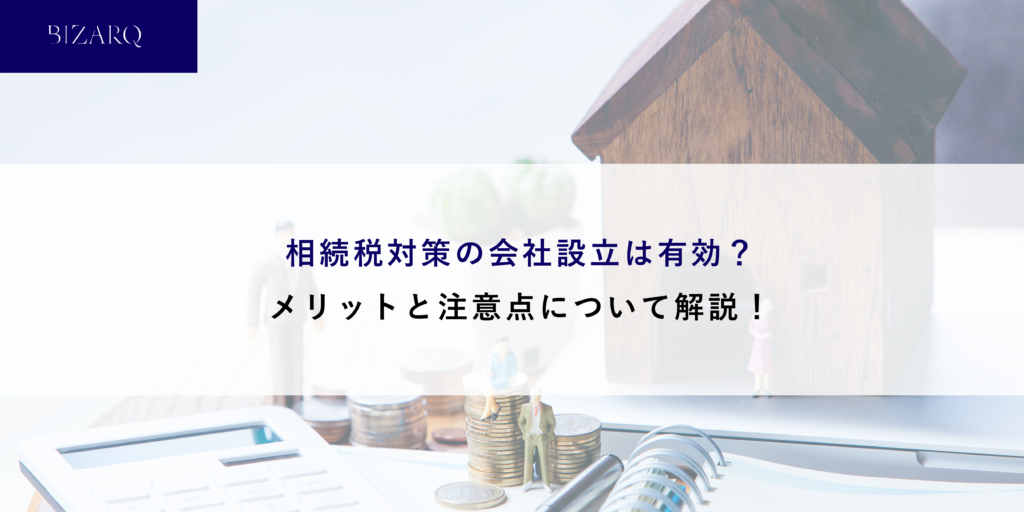
一般的に会社設立とは、法務局における登記申請手続きを意味します。
すなわち会社設立の登記申請が無事に受理されれば、会社設立自体は完了となります。
しかし、会社として活動を行うためには会社設立後もさまざまな届出が必要です。
今回は会社設立後に必要な届出について、提出先ごとに詳しく解説します。
会社設立後に必要な手続き全般については以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
CONTENTS
会社設立後に必要な届出 税務署編
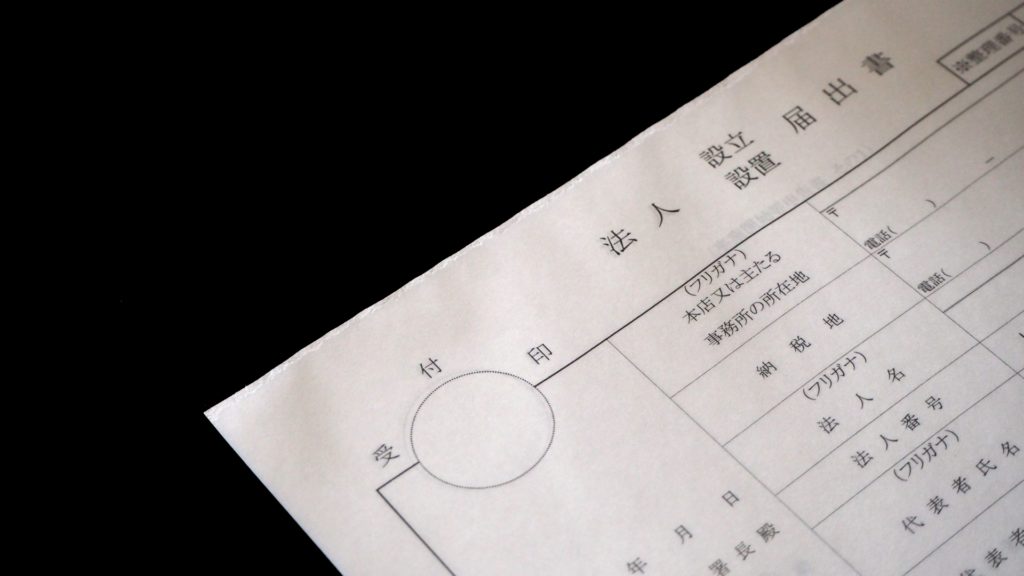
まずは会社設立後に税務署へ届出が必要な書類について紹介します。
なお、いずれの届出も本店所在地の管轄税務署が提出先となります。
【必須】法人設立届出書
法人設立届出書はすべての会社において必須の届出です。
本店所在地・法人番号・事業目的などの必要事項を、定款および登記簿謄本の内容と同じように記載します。
定款等の写しや登記簿謄本の添付も必要です。
法人設立届出書は、会社設立後2ヶ月以内に提出する必要があります。
【必須】給与支払事務所等の開設届出書
給与支払事務所等の開設届出書とは、文字通り給与支払いを行う事務所を開設した場合に提出が必要な書類です。
会社設立直後に従業員を雇っておらず社長一人であっても、会社から役員報酬の支払いが行われる場合は届出が必要となります。
給与支払事務所等の開設届出書は、会社設立から1ヶ月以内に提出が必要です。
法人設立届出書よりも提出期限が短く設定されている点にご注意ください。
実務上、法人設立届出書・給与支払事務所等の開設届出書いずれも、会社設立から1ヶ月以内に一緒に出すケースがほとんどです。
【推奨】青色申告の承認申請書
青色申告の承認申請書は、青色申告を行うために提出が必要な書類です。
青色申告にしない場合は提出の必要がありませんが、青色申告には特別控除や赤字の繰越などさまざまなメリットがあります。
そのため必須の届出とあわせて青色申告の承認申請書も提出し、設立1期目より青色申告にするのがおすすめです。
設立1期目から青色申告にするためには、会社設立から3ヶ月以内に提出する必要があります。
この期日を過ぎてしまうと、当該事業年度は白色申告となってしまうため注意が必要です。
【推奨】源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書
会社や給与や報酬から控除する源泉所得税は、原則徴収した月の翌月10日が納期限です。
しかし、常時雇用する従業員が10人未満の場合、源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書を提出すれば、年2回に分けてまとめての納付が可能になります。
規模の小さい会社だと、毎月の源泉所得税納付手続きが手間や負担になることがあります。
そのため、その他の届出とあわせて源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書も提出するのがおすすめです。
源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書に明確な期日はなく、提出した翌月に支払う給与等から適用となる仕組みです。
会社設立後に必要な届出 自治体編

続けて会社設立後に自治体へ必要な届出について解説します。
【必須】都道府県税事務所 法人設立届出書
地方自治体には地方税に関する届出を行う必要があります。
そのひとつが、都道府県税事務所へ提出する法人設立届出書です。
都道府県税事務所へ提出する法人設立届出書に記載する内容は、税務署へ提出する法人設立届出書と大きな違いはありません。
ただし、細かなフォーマットや記載事項、提出期日などは自治体によって異なります。
必ず自治体の公式サイトなどでご確認ください。
【必須】市町村役場 法人設立届出書
市町村役場にも法人設立届出書の提出が必要です。
都道府県税事務所と同様、フォーマットや期日などは自治体の公式サイトでご確認ください。
なお、本店所在地が東京23区の場合、法人設立届出書は都税事務所への届出のみとなります。
区役所への提出は必要ありません。
会社設立後に必要な届出 年金事務所編

続いて年金事務所に必要な届出について解説します。
【必須】健康保険・厚生年金保険新規適用届
健康保険・厚生年金保険新規適用届は、健康保険および厚生年金保険への加入義務がある事務所を開設した場合に必要な届出です。
法人は健康保険および厚生年金保険への加入が義務付けられています。
従業員を雇っておらず社長一人の会社にも加入義務があるため、会社設立をしたら必ず健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出しましょう。
健康保険・厚生年金保険新規適用届の提出期日は、会社設立から5日以内です。
事務所所在地を管轄する年金事務所または事務センターへ提出します。
添付書類として、登記簿謄本の原本および法人番号指定通知書等のコピーが必要です。
【必須】健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届は、新たに健康保険および厚生年金保険へ加入するべき従業員が生じた際に提出が必要な書類です。
従業員がおらず社長一人の場合でも、社長が社会保険の被保険者になるために提出する必要があります。
なお、左上の「事業所整理番号」および「事業所番号」は、健康保険・厚生年金保険新規適用届が受理された後に発行されるものです。
会社設立直後の段階では番号がないため、空欄で問題ありません。
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届の提出期限は、新たに健康保険および厚生年金保険するべき人が生じてから5日以内です。
【ケースによる】健康保険被扶養者(異動)届
新たに被保険者となった人に扶養家族がいる場合や、被扶養者の変更・削除などを行う場合、健康保険被扶養者(異動)届の提出が必要です。
戸籍謄本や年収を証明する書類を添付する必要があります。要件によっては、追加の書類が必要となるケースもあります。
提出期限は事実が発生してから5日以内です。
会社設立後に必要な届出 労働基準監督署・ハローワーク編

会社設立の段階で労働保険に加入する場合は、労働基準監督署・ハローワークへの届出も必要です。
これまでに紹介した税務署・自治体・年金事務所への届出は、会社設立後に必ず発生します。
一方で労働基準監督署・ハローワークへの届出は、労災保険および雇用保険の加入義務が発生しない限りは必要ありません。
労災保険は、従業員を雇用した場合に必ず加入義務が生じます。
従業員の年齢や労働時間は問いません。
一方で雇用保険は、所定労働時間が短い・一定以上の年齢・季節的業務かつ短期雇用など、一定のケースに該当しない従業員を雇った場合に加入義務が生じます。
労災保険の加入義務が生じても、雇用保険にも必ず加入しなければならないわけではないということです。
会社設立時に従業員を雇用しない場合、労働基準監督署・ハローワークへの届出は不要です。
今回は会社設立時に従業員を雇用する場合の、労働基準監督署・ハローワークへの届出について解説します。
労働基準監督署に提出する書類
労働基準監督署に提出する書類は以下の通りです。
- ・適用事業報告書
- 従業員の雇用後、すみやかに提出が必要です。
- ・労働保険 保険関係成立届
- 従業員を雇用した翌日から10日以内に提出する必要があります。
- ・労働保険 概算保険料申告書
- 労働保険料の見込み額を納付ための書類です。
- 従業員を雇用した翌日から50日以内に提出します。
- ・就業規則(変更)届
- 常時10人以上の従業員を雇用した際、すみやかに提出が必要です。
ハローワークに提出する書類
ハローワークに提出する書類は以下の2つです。
- ・雇用保険適用事業所設置届
- 従業員を雇用した翌日から10日以内に提出する必要があります。
- ・雇用保険被保険者資格取得届
- 従業員を雇用した翌日から10日以内に提出が必要です。
まとめ
法務局における会社設立登記が完了しても、すぐに会社として事業活動ができるわけではありません。
税務署・自治体・年金事務所など複数個所へさまざまな届出を行う必要があります。
届出は種類が多い上に内容によってルールが違い、提出期限も厳格です。
漏れなく届出するためには、事前に内容や期日を確認するのはもちろんのこと、専門家のサポートを受けるのもひとつの手段といえるでしょう。
会社設立後の届出について疑問や不安があれば、ぜひ専門家へご相談ください。
会社設立をワンストップでサポート
税務相談や節税対策もBIZARQにお任せください。
全国オンライン対応・ご相談は無料です。

記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士