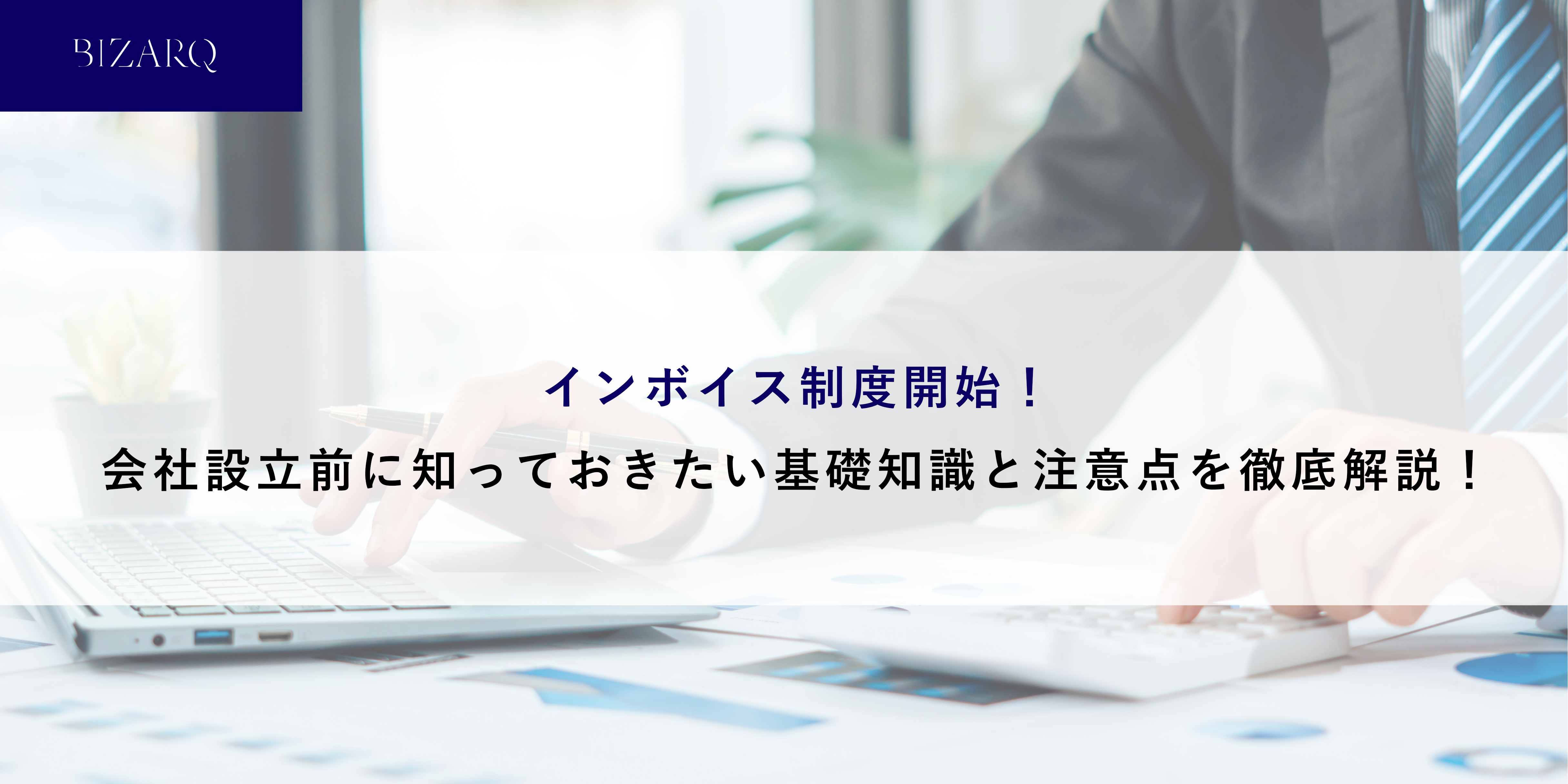2023年10月1日からインボイス制度が開始されました。
インボイス制度は消費税の仕入税額控除に関する制度であり、多くの事業者に多大な影響を与えます。
基本的に、会社設立直後は消費税の免税事業者となる要件を満たします。
インボイス制度の開始後も消費税の免税要件に変更はないため、設立直後の会社は消費税の免税事業者であるケースがほとんどです。
しかし、インボイス制度の導入により、免税事業者のままでいると案件や取引先の獲得が不利になる恐れがあると考えられます。
今回はインボイス制度について、会社設立前に知っておくべき基本知識や注意点を詳しく解説します。
消費税の免税要件については以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。
CONTENTS
会社設立前に知っておきたいインボイスの基礎知識

はじめに、会社設立前に知っておきたいインボイスの基礎知識を紹介します。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除に関する制度です。
インボイス制度の開始後、仕入税額控除の計算に含めることができるのは適格請求書等(インボイス)を保存している取引のみとなります。
そもそも仕入税額控除とは、売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額を引いて納付税額を計算する仕組みを意味する言葉です。
インボイス制度の開始前は、消費税の課税対象となる仕入や経費の支払いはすべて仕入税額控除の計算に含めることができました。
しかしインボイス制度の開始後、仕入れ税額控除の対象となるのが、インボイスを保管している取引のみとなりました。
以下のケースを例に、インボイス制度の開始前と開始後で消費税額がどのように変わるかを紹介します。
- ・売上に係る消費税額:100万円
- ・仕入に係る消費税額:70万円
- うちインボイスを保管していない取引にかかる消費税:20万円
インボイス制度の開始前の場合、上記条件では消費税の納付額は以下のようになります。
- 100万円-70万円=30万円
一方インボイス制度の開始後、インボイスを保管していない取引にかかる消費税は売上に係る消費税額から控除できません。
そのため納付する消費税の額は以下のようになります。
- 100万円-(70万円-20万円)=50万円
インボイス制度の開始によって、仕入税額控除の対象になる取引の範囲が狭くなったのです。
インボイスを発行できるのは消費税の課税事業者のみ
インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。
そして、適格請求書発行事業者の登録ができるのは消費税の課税事業者のみです。
免税事業者は適格請求書発行事業者の登録ができないため、必然的にインボイスの発行ができません。
インボイス制度が会社設立に与える影響

インボイス制度が会社設立にどのような影響を与えるか、現時点で考えられるものを紹介します。
【前提】会社設立直後は原則として消費税の免税事業者
前提として、会社設立直後は消費税の納付義務が免除されるケースがほとんどです。
以下2つの要件を満たす法人は、消費税の納税義務が免除されます。
- ・その事業年度の開始日における資本金が1,000万円未満の場合
- ・基準期間の課税売上高が1,000万円以下
基準期間とはその年の前々事業年度です。会社設立1期目は基準期間が存在しません。
そのため、設立時の資本金が1,000万円未満であれば、会社設立1期目は消費税の免税事業者になります。
設立2期目も、下記いずれかの要件を満たせば消費税の納税義務が免除されます。
- ・特定期間における課税売上高が1,000万円以下
- ・特定期間における給与の支払額が1,000万円以下
特定期間とは、その事業年度の前事業年度の開始日から6ヶ月間です。
特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与の支払額が1,000万円以下であれば納税義務の免除要件を満たすとみなされます。
なお、消費税の免除を受けるために必要な手続きは特にありません。
要件を満たしていれば自動的に消費税の免税事業者となります。
免税事業者は案件や取引先の獲得が不利になる恐れがある
インボイス制度の導入後も、消費税の免除事業者になる要件に変わりはありません。
そのため、インボイス制度の開始前と同様に会社設立直後は消費税の免税事業者になるケースが多いです。
ただし、インボイス制度の導入後も免税事業者のままでいると、新規案件や取引先の獲得がしにくくなる可能性があります。
前章で、インボイス制度の開始前と開始後で納付税額が変わるケースについて、具体例を用いて紹介しました。
インボイスを保管していない取引は仕入税額控除の対象にならないため、買い手は消費税分を負担する必要があります。
そのため、今後は買い手となる事業者が適格請求書発行事業者との取引を優先するようになる可能性が高いでしょう。
インボイスを発行できない消費税の免税事業者は、案件や取引先の獲得が不利になってしまう恐れがあります。
会社設立直後は新規案件の獲得が必要な時期です。しかし、免税事業者で居続けると新規案件の獲得が難しくなってしまう可能性が考えられます。
そのため、会社設立直後であっても、あえて課税事業者となって適格請求書発行事業者の登録をした方がメリットが大きいケースも考えられます。
【参考】インボイスの影響を受けにくい法人
以下いずれかの条件を満たす法人は、インボイスの影響を比較的受けにくいと考えられます。
個人を対象とした事業を営む法人
インボイスは仕入税額控除に関する制度です。一般消費者である個人の買い物には影響しません。
そのため、個人を対象とした事業を営む法人は、インボイスを発行できなくても問題ない可能性が高いと考えられます。
取引先が小規模および零細企業
小規模の会社は消費税の計算方法として簡易課税を選択しているケースが多いです。
簡易課税の場合は仕入税額控除についてインボイスの保管有無は関係ありません。
そのため、取引先が小規模および零細企業の場合も、インボイスの発行可否が取引に与える影響は小さいと考えられます。
ただし、小規模および零細企業のすべてが簡易課税の適用を受けているとは限らないため注意が必要です。
会社設立時に押さえておくべきインボイスに関する注意事項

インボイスについて、会社設立時に押さえておくべき注意事項を紹介します。
【原則】課税事業者になるためには手続きが必要
原則として、消費税の免税要件を満たす事業者が課税事業者になるためには、「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。
提出期日は適用を受けようとする年の開始日の前日となります。
ただし、インボイス制度の開始日である2023年10月1日から2029年9月30日までの日が属する課税期間中は例外です。
この期間中は適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日を記載することで、記載された登録希望日から課税事業者になったとみなされます。
そのため、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける場合、届出書の提出は免除されます。
事前に簡易課税と原則課税どちらにするか決めておく
消費税の課税事業者になる前に、簡易課税と原則課税どちらにするか決めておく必要があります。
原則課税とは、売上げに係る消費税額から仕入れにかかる消費税を引いた額を納付税額とする方法です。
「インボイス制度とは」の項で紹介した例では、原則課税の方法で消費税を計算しています。
簡易課税は、売上げに係る消費税額に事業区分に応じて設定されたみなし仕入率を乗じた額を仕入れに係る消費税額とみなして計算する方法です。
計算式で表すと以下のようになります。
- 消費税の納付額=売上げに係る消費税額-売上げに係る消費税額×みなし仕入率
仕入れに係る消費税額として実際にいくらかかったかは関係ありません。
基準期間の課税売上高が5,000万円以下であれば、簡易課税制度の選択が可能です。
同じ会社でも、原則課税と簡易課税どちらで計算するかによって消費税の納付額が変わります。
どちらの方が有利であるかはケースによって異なるため、自社に合う方を選択する必要があります。
簡易課税の適用を受けるには届け出が必要なため、会社設立前に決めておくと安心です。
なお、簡易課税の適用から2年を経過するまでは原則課税への切り替えができません。
適格請求書発行事業者の登録申請が必要
会社設立1期目からインボイスを発行するためには、課税期間の末日までに登録申請書の提出が必要です。
適格請求書発行事業者の登録申請をしなければインボイスの発行ができません。
登録の効力は原則として登録日から発生します。
ただし新設法人の場合、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに手続きをすれば、事業を開始した日の属する課税期間の初日に登録したものとみなされます。
登録申請書の提出方法は郵送とe-Taxの2種類です。
e-Taxで申請した場合、適格請求書発行事業者の登録番号が記載された通知書をデータで受け取ることができます。
登録番号はインボイスに記載が必要な事項のため、紛失の恐れがないデータで受け取るのが安心です。
郵送で提出する場合は登録通知書が書面で送付されます。
まとめ
多くの場合、会社設立直後は消費税の免税事業者となる要件を満たします。
しかし、消費税の免税事業者はインボイスの発行ができません。
インボイスの発行ができない場合、案件や取引先の獲得が不利になる可能性があります。
会社設立直後は案件獲得の必要性が高い大切な時期であるため、あえて消費税の課税事業者になった方が良い場合もあります。
インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者の登録手続きが必要です。
消費税の課税事業者になるのであれば、原則課税と簡易課税のどちら選ぶか決める必要もあります。
インボイス制度の仕組みや原則課税と簡易課税の選択等、消費税についてお悩みがあれば専門家である税理士に相談すると的確なアドバイスがもらえるでしょう。
会社設立をワンストップでサポート
税務相談や節税対策もBIZARQにお任せください。
全国オンライン対応・ご相談は無料です。

記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士