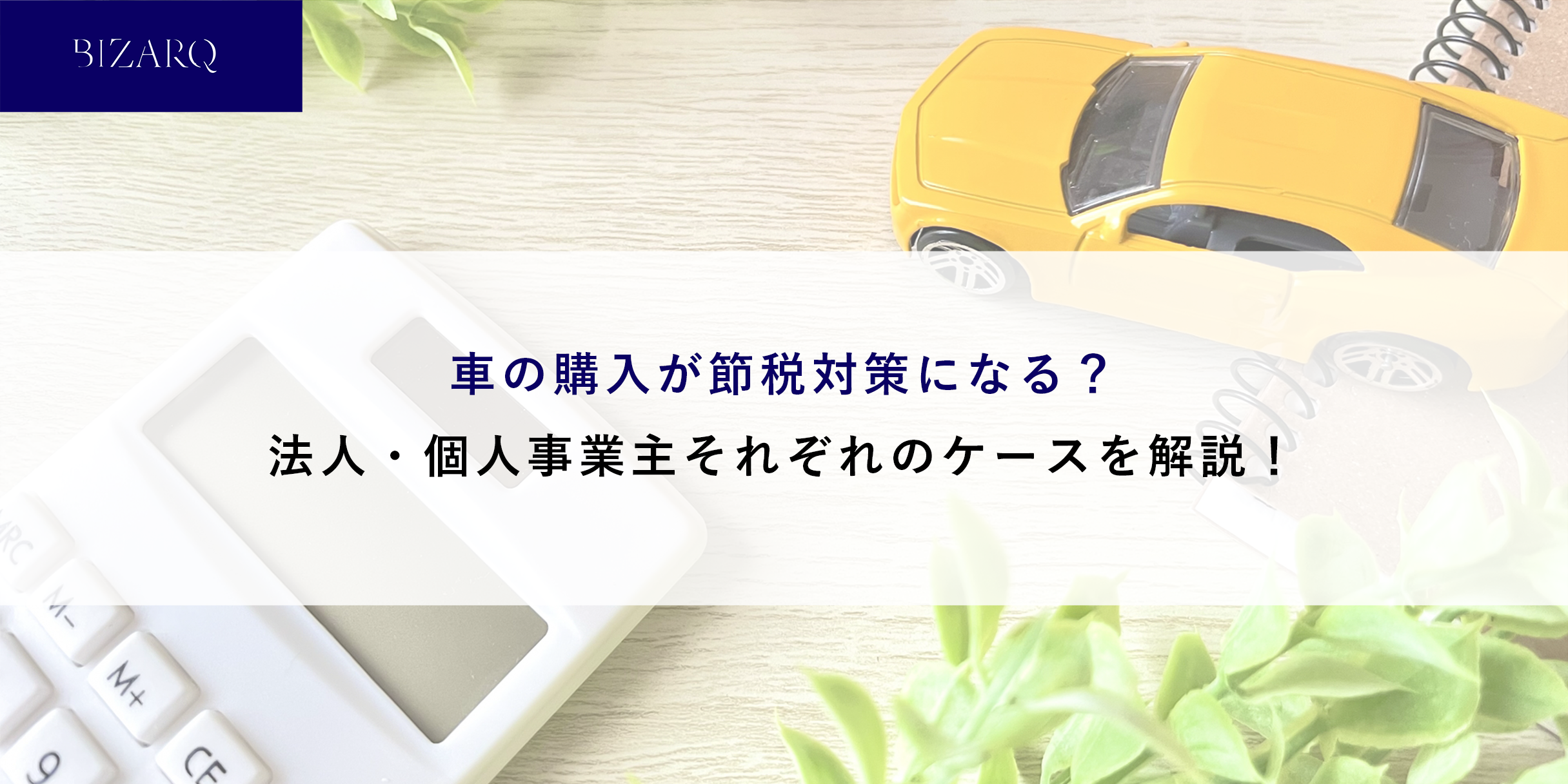事業に関連するモノを購入したり、あえて大きな支出をするのは、節税対策の代表的なテクニックのひとつです。
なかでも車は購入は関連する諸費用ともに高額であり、上手く活用すれば大きな節税効果が得られる可能性があります。
しかし、車の購入で節税効果を得るためには、正しい知識をつけた上でポイントをしっかり押さえることが大切です。
今回は車による節税対策について、法人・個人事業主それぞれのケースを紹介します。
法人・個人事業主の節税テクニック全般について以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。
CONTENTS
車の購入が節税になる理由

結論として、車の購入が節税につながるケースは多いです。
車が節税対策として効果的な理由について解説します。
経費にできる支出が増えるため
業務に使う車であれば、購入費や車に関する諸費用を経費として計上できます。
経費が増える分所得が小さくなるため、節税に効果的です。
車に関連する支出のうち、経費にできるものの具体例を紹介します。
駐車場代
取引先への訪問など、業務に関連する移動に際して駐車場を使った場合、駐車場代は経費として計上可能です。
ガソリン代
社用車のように完全に事業用の車であれば、ガソリン代は全額経費に計上できます。
プライベートでも使う車の場合、仕事とプライベートでの家事按分が必要です。
車検費用
ガソリン代と同様、プライベートで使っているか否かによって、経費にできる金額の割合が変わります。
自動車税、自動車重量税などの税金
ガソリン代・車検費用と同様です。
自賠責保険、任意保険料などの保険料
車関連で加入している保険の支払いも経費として計上できます。
車の購入費用は減価償却が必要
車の購入価額は、購入した年に全額費用計上できるわけではありません。
車は減価償却の対象となる資産です。
減価償却とは、固定資産の取得価額を耐用年数に応じて配分し、少しずつ費用計上する会計処理です。
車を含めた高額の固定資産は数年にわたって使用することができ、購入した年以外の利益にもつながります。
そのため減価償却を行い、使用できる期間で少しずつ経費として計上していく必要があるのです。
減価償却には大きく2つの方法があります。
1つは定額法です。
定額法とは、固定資産の取得価額に償却率を乗じた額を減価償却費として計上する方法です。
減価償却費は以下の式で計算します。
減価償却費=固定資産の取得価額×定額法の償却率
定額法の場合、計上する減価償却費は毎期同額です。
個人事業主は原則として、定額法で減価償却を行います。
またソフトウェア等の無形固定資産や建物・構造物・生物は、法人でも定額法を使います。
もう1つの方法は、定率法です。
定率法では固定資産の残存価額(未償却残高)に償却率を乗じた額を減価償却費として計上します。
計算式は以下の通りです。
減価償却費=固定資産の残存価額×定率法の償却率
定率法の場合、購入した年に計上する減価償却費が最も大きく、以降は減っていきます。
法人は基本的に定率法を用います。
計算に用いる償却率は固定資産の種類ごとに定められており、国税庁の公式サイトで確認可能です。
法人が車で節税対策をする上でのポイント

法人が車を購入するのであれば、新車ではなく中古車のほうが、大きな節税効果を得られる可能性が高いです。
中古車のほうが節税につながる理由として、減価償却の仕組みが挙げられます。
減価償却は固定資産の購入価額を、耐用年数に応じて少しずつ費用にする会計処理だと紹介しました。
耐用年数は固定資産の種類によって明確に決められており、普通自動車は6年、軽自動車は4年です。
しかし、購入した固定資産が中古の場合、耐用年数は以下の算式で求められます。
購入した中古固定資産の耐用年数=新品の場合の耐用年数-経過年数+経過年数×20%
たとえば2年落ちの中古車を購入した場合、耐用年数は 6-2+2×20%=4.4年、1年未満の部分は切り捨てとなるため、耐用年数は4年です。
このように中古車は新車よりも耐用年数が短くなります。
減価償却は購入価額を耐用年数に応じて配分するため、耐用年数が短いほど1回に計上できる金額が大きくなるのです。
中古車でも、走行距離や使い方によっては新車並みに良い状態のケースがあります。節税を狙うのであれば、中古車を購入するのがおすすめです。
なお、もっとも節税効果が狙えるのは4年落ちの中古車です。
4年落ちの中古車を購入した場合、耐用年数は6-4+4×20%=2.8年、端数を切り捨てて2年になります。
法人の場合、減価償却の方法は原則として定率法が適用されます。定率法は残存価値に対して一定の割合(償却率)を乗じて減価償却を行う方法です。
そんな定率法ですが、耐用年数が2年の場合、償却率が100%になります。すなわち4年落ちの中古車は耐用年数が2年になるため、購入した年に全額の経費計上が可能なのです。
法人が4年落ちの中古車を購入すれば、購入した年に購入価額を全額費用計上できるため経費が大きくなり、結果として大きな節税につながります。
個人事業主が車で節税対策をするためのポイント

個人事業主も車を使った節税対策ができますが、法人とは異なるポイントを押さえる必要があります。詳しく解説します。
購入した年に得られる節税効果は法人よりも少なくなる
個人事業主も法人と同様、耐用年数が短い中古車を購入した方が、1回あたりに計上できる減価償却費が大きくなります。
そのため、中古車の方が節税効果が高いのは法人と同じです。
しかし個人事業主の場合、前述のように原則として定額法で減価償却を行います。
そして、定額法は定率法よりも、減価償却によって得られる節税効果が少なめです。
法人に適用される定率法では、残存価額に償却率を乗じて減価償却費を計算します。
残存価額が大きいほど計上する減価償却費も大きくなるため、購入した年に計上する減価償却費が最も大きくなる仕組みです。
一方、個人事業主に適用される定額法は、購入価額を耐用年数で分割し、毎期一定の額を減価償却費として費用計上します。
したがって、購入した年に計上できる減価償却費は、定率法を用いる場合よりも少なくなります。
また、法人に適用される定率法では、耐用年数2年の場合は償却率が100%になるため、4年落ちの中古車であれば購入した年に全額費用計上できると紹介しました。
一方で定額法の場合、購入したのが4年落ちの中古車であっても、耐用年数の2年で同額ずつ経費計上する必要があります。
当然ですが、購入した年に計上できる減価償却費は全額を経費計上できる定率法よりも少なくなります。
以上の理由から、定率法で計算する法人よりも、定額法を使う個人事業主の方が購入した年に得られる節税効果が少なくなる傾向にあります。
なお、個人事業主でも期日までに所定の申告書を税務署に提出すれば、定率法による減価償却が可能になります。
プライベートでも使う場合は按分計算が必要
購入した車を事業とプライベートの両方で使っている場合、事業部分とプライベート部分を明確にする按分計算が必要です。
個人事業主の場合、車を事業とプライベートの両方に使うケースが多いでしょう。
この場合、経費として計上できるのは事業に関する支出のみです。
車に限らず、事業とプライベートが混ざった支出については、事業部分のみを経費として計上する必要があります。
事業とプライベートの支出を分ける計算を家事按分といいます。
家事按分で用いる割合に、法律などによる明確な定めはありません。客観的に説明できる・説得力のある割合を用いる必要があります。
車の場合、走行距離で按分するケースが多いです。走行距離全体のうち事業に関する走行距離が占める割合を計算し、その割合を使って家事按分を行います。
走行距離で按分する場合、計算根拠として走行距離をしっかり記録する必要があります。
なおETCや駐車場など、いつ・どこで・何のために使ったか明確な支出は、家事按分の必要がありません。
事業で使った分について領収書やレシートを残しておけば計算根拠となります。レシートの裏面に、訪問先や訪問理由などをメモしておくと安心です。
青色申告を行う
車による節税効果を最大限得るためには、青色申告を行う必要があります。
白色申告の場合、事業利用割合が50%を下回る場合は家事按分ができず、経費として計上できません。
事業・プライベートの両方で使う車であっても、プライベートの方が多く使っている場合、事業での使用があっても一切経費計上ができないのです。
青色申告には税務上の優遇措置が多く存在します。
車の節税効果という面に限らず、個人事業主が節税対策をするのであれば青色申告にするのがおすすめです。
青色申告への切り替えは、青色申告承認申請書を期日までに税務署へ提出するだけで完了します。
また青色申告を行うためには、以下3つの義務を果たす必要があります。
こちらも必ず実施しましょう。
・複式簿記による帳簿付けをする
・確定申告の際、青色申告決算書を併せて提出する
・帳簿書類を7年(一部は5年)保管する
会社員でも車による節税は可能?

会社員が副業をしており、副業に際して車を使った場合は、その分の支出は経費計上ができます。押さえるべきポイントは個人事業主の場合と同じです。
副業をしておらず給与所得だけの場合、原則として車での節税はできません。
ただし、通勤や出張などに車を使っていて会社から支給を受けていない場合、所得控除を受けられるケースもあります。
仕事に関する支出の自己負担が一定額を超えた場合に、対象の支出を所得控除の対象にできる制度を、特定支出控除といいます。
しかし、特定支出控除は申請の手間が大きく節税効果は小さいといった理由から、適用されるケースがそれほど多くありません。
そのため、給与所得のみの会社員が車で節税できる可能性はあまり高くないといえるでしょう。
まとめ
事業で車を使う場合、車関連の支出について経費計上が可能です。経費が増える分所得が小さくなるため節税効果が得られます。
車で節税するためには、減価償却や節税について理解を深め、正しい方法で行うことが大切です。
特に個人事業主は法人よりも押さえるべきポイントが多いため、事前にしっかり確認しましょう。
車を使った節税について疑問や不安があれば、税理士などの専門家へお気軽にご相談ください。
法人・個人事業主の節税対策は
BIZARQにお任せください。
全国オンライン対応・ご相談は無料です。

記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士