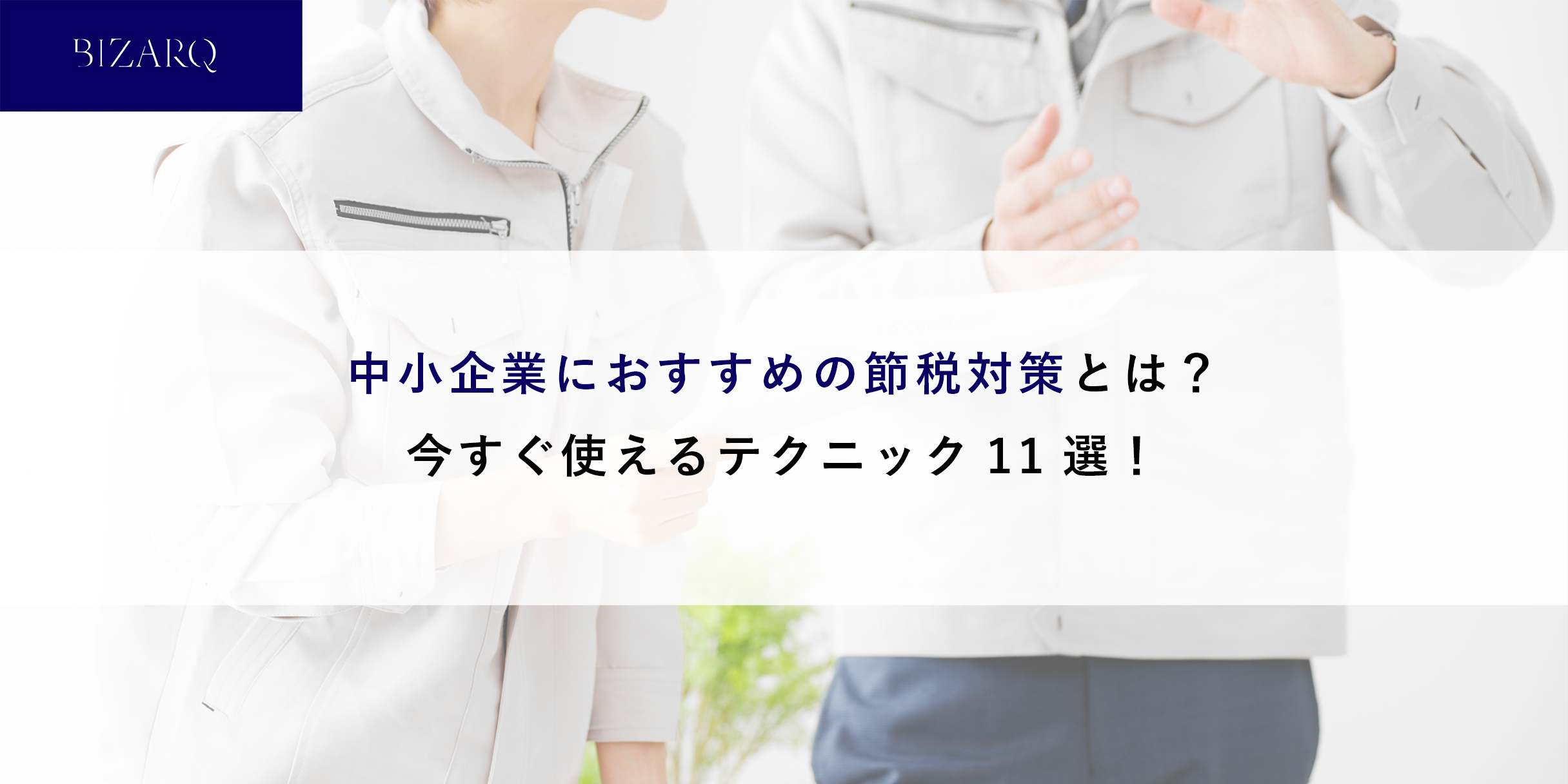中小企業は大企業と比べて税負担が大きく、資金繰りの面でもシビアな経営を強いられる傾向にあります。
納税は避けられないものですが、工夫次第で税金の額を抑えることは可能です。
今回は、中小企業におすすめの節税対策をご紹介します。
法人全般の節税テクニックについてはこちらの記事で解説しています。
個人事業主の節税テクニックについてはこちらの記事で解説しています。
CONTENTS
中小企業の節税対策として効果的な方法を紹介

中小企業ができる節税対策について、具体的な方法を紹介します。
法人保険に加入する
法人保険とは、法人格を契約者とした法人向けの生命保険です。
事業保障の他、経営者や役員、従業員向けの保障、退職金など従業員の福利厚生としても利用できる保障など、法人特有の様々なリスクに備える商品があります。
これらの保険料は、一部または全額損金に算入できるため、節税に繋がります。
しかし、2019年に法人保険の損金取扱いに関するルールが変更となり、節税のみを目的とした法人保険の加入は実質不可となりました。
法人保険の目的は企業の経営リスクに備えることであり、節税はあくまで副次的な効果です。そのことをきちんと理解した上で加入を検討しましょう。
法人向け保険については、以下の記事で詳しく解説しています。
役員報酬を上手く活用する
役員報酬を上手く活用できれば、大きな節税効果が期待できます。
ただし、役員報酬は従業員に支払う給与と違いルールが非常に厳格です。
役員報酬を活用した節税を行う際は、必ず関連する法やルールをしっかり確認しましょう。
今回は役員報酬を活用した節税テクニックを2つ紹介します。
役員報酬については、以下の記事で詳しく解説しています。
事前確定届出給与を支給する
事前確定届出給与とは役員に対する賞与(ボーナス)のようなものです。
役員に対しても通常の報酬だけでなくボーナスを支給すれば、その分経費が大きくなります。
なお、事前確定届出給与は事前に税務署へ支払日・支払額の届出が必要です。
届出書の内容と実際の支給日や支給額に少しでも相違がある場合、該当の会計期間に支給した事前確定届出給与すべてが損金不算入になるためご注意ください。
経営者の家族を役員にして役員報酬を分散させる
所得税は、所得が多いほど税率が高くなる累計課税です。
そのため、経営者一人に報酬を集中させるのでなく、配偶者など家族を役員にして所得を分散させた方が、総収入は変わらずに税金を抑えることができます。
ただし、勤務の実態がなければ役員報酬は認められないため注意しましょう。
共済を活用する
中小企業が加入できる共済の活用も節税に効果的です。
その代表として挙げられるのが、小規模企業共済と、中小企業倒産防止共済です。
これらは独立行政法人である中小機構が運営しているため、民間の保険会社のような倒産リスクがなく安心です。
以下に詳しく解説します。
小規模企業共済
中小企業の経営者や個人事業主が自身の退職金を積み立てるための制度です。
掛金は全額控除対象となります。
廃業時や退職時に解約手当金を受け取ることができますが、退職所得または雑所得として課税対象となる点は認識しておきましょう。
中小企業倒産防止共済
1年以上事業を継続している法人や個人事業主が加入できます。
こちらも掛け金は全額損金として経費計上可能です。
解約手当金は雑収入扱いで課税対象となるため、退職金や修繕など損金として大きな支出があるタイミングを狙って解約すると、税額を抑えることができます。
設備・人的投資を行う
会社の設備や人材へ投資すると控除が受けられるため節税になります。
それぞれ利用できる制度をご紹介します。
中小企業経営強化税制
設備投資による企業力強化や生産性向上の支援を目的とした、特別償却・税額控除制度です。
一定の要件を満たすことで、取得価格の最大10%の税額控除が受けられます。
所得拡大促進税制
前年度より給与を増加させた企業に対し、増額分の一部を控除する制度です。
一定の要件を満たすことで、最大25%の税額控除が受けられます。
雇用促進税制
人材の新規採用を積極的に行う企業に対し、給与支給額の一部を控除する制度です。
一定の要件を満たすことで、一人当たり最大90万円の税額控除が受けられます。
これらの優遇措置は、期間限定で行われることがほとんどです。
中小企業省が発行する「中小企業施策利用ガイドブック」を参照するなどして、申請前に必ず最新の情報をチェックしましょう。
少額償却資産を活用する
10万円未満のものは消耗品費として経費にできますが、10万円以上のものは減価償却資産として数年かけて資産計上する必要があります。
しかし、中小企業の場合は少額減価償却資産の特例を申請することで、30万円未満の物を一括で経費にすることができます。
10~30万円の物品で事業に必要なものがある場合は、この制度を活用することで節税となります。
申請の際は明細が必要ですので、申告書へ忘れず添付しましょう。
福利厚生を充実させる
福利厚生費は経費として計上可能です。
具体的な内容として以下の例が挙げられます。
- ・懇親会
- ・レクリエーション
- ・社員旅行
- ・健康診断
福利厚生を充実させる方法は、節税になるだけでなく、社員のモチベーション向上と社内の雰囲気づくりにも役立ちます。
また、福利厚生の内容そのものを充実させるだけでなく、金額を見直し必要であれば改訂するもの良いでしょう。
なお、福利厚生費として経費計上するためには、職位に関わらず全ての社員に平等の福利厚生を付与する必要があります。
別会社を設立する
通常、法人税率は23.2%ですが、利益が800万円以下の中小企業には15%の軽減税率が適用されるためです。
節税目的で別会社を新たに立ち上げる際は、運営方針を含め税理士などのプロに相談するのがおすすめです。
固定資産を見直す
使用していない物や廃棄済みの資材などが帳簿上残っていないか、決算前に確認しましょう。
帳簿から削除することで償却資産税の負担を減らせるだけでなく、除却損として損金計上できることもあります。
常日頃から帳簿と実態を一致させておくことも、節税のために非常に重要です。
また、新たに固定資産を購入する際に中古資産を選ぶのも効果的です。
中古でも新品同様に状態の良い固定資産は多く存在します。
新品にこだわらず中古も選択肢に入れることで、購入費を抑えつつも状態の良い固定資産が手に入る可能性があるのです。
また、中古資産は減価償却において新品よりも短い耐用年数で計算します。
購入価額および残りの耐用年数によっては、購入した年に高額の減価償却費を計上できるため節税に効果的です。
不要な固定資産の除却と中古資産の購入は、いずれも簡単に節税効果を得られる方法です。
社長所有の不動産を会社へ貸し出す
社長個人が所有する不動産を会社に貸し付け、社宅や事業所として利用します。
会社から社長に支払う家賃は経費として損金計上できるため、節税となるのです。
しかし、社長が受け取った不動産収入は所得税の対象となるため、結果的に節税にならない可能性もあります。全体のバランスを考えて運用を行いましょう。
車両を社用車に切り替える
社長が個人で所有している車を法人に売却し社用車にすることで、節税となります。
中古車扱いとなり、新車より短い年数で減価償却できる他、ガソリン代やメンテナンス代なども経費として申請することができます。
保険も法人名義に変更するのが望ましいですが、業務に使用しているという実態が伴っていれば個人名義のままでも経費にできます。
車両を活用した節税については以下の記事で詳しく解説しています。
出張手当を支給する
出張のある業種であれば、出張手当の支給を検討しましょう。
出張手当は、会社側は経費に出来て、支給された従業員側は非課税になるという非常にメリットの多い制度です。
ただし、出張旅費規程を制定すること、全従業員に同じ条件で支給することなど諸条件があるため、きちんと確認しましょう。
まとめ
中小企業ができる節税対策について述べてきました。
節税対策は中小企業にとって会社を維持するために非常に重要な施策です。
しかし、あまりに行き過ぎた節税はトータルで考えた時に逆に損失に繋がるリスクがあり、また税務署から指摘が入る可能性もあります。
きちんと税法に則り、節度を守った節税対策を心がけましょう。
法人・個人事業主の節税対策は
BIZARQにお任せください。
全国オンライン対応・ご相談は無料です。

記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士