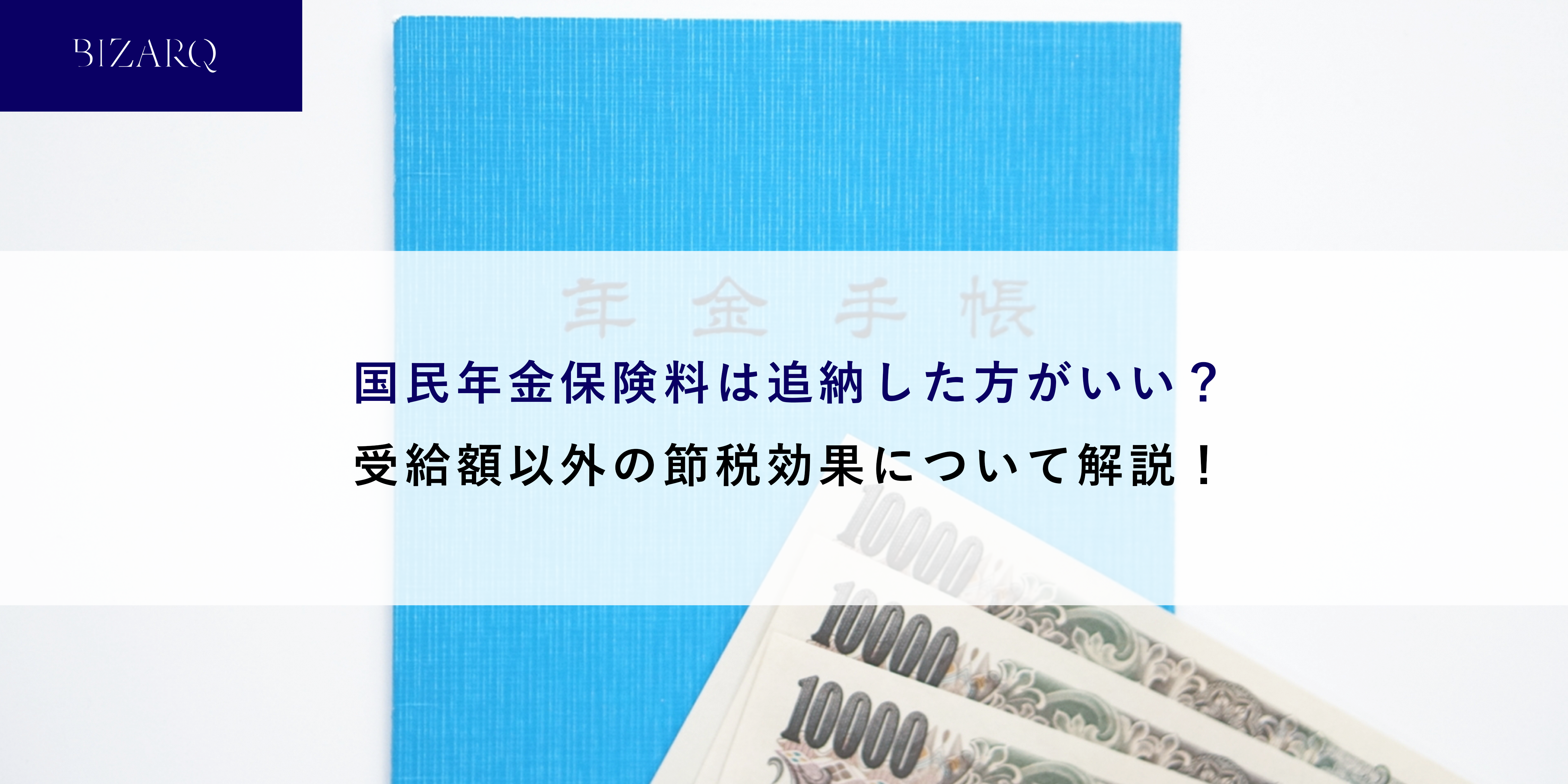国民年金保険料の追納とは、免除・猶予された国民年金保険料を後から納付する行為です。
国民年金に追納の義務はありませんが、追納によって、将来の年金受給額が増える・追納した年に節税効果を得られるというメリットがあります。
支出を伴うため自身の経済状況を考慮した上で判断する必要がありますが、可能であれば追納するのがおすすめします。
ただし、メリットだけでなく注意点の確認も事前に必要です。
今回は国民年金保険料の追納について、概要やメリット・注意点を詳しく解説します。
なお、公的年金(老齢年金)は課税対象です。年金にかかる所得税については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。
CONTENTS
国民年金保険料の追納の概要

はじめに、国民年金保険料の追納の概要を解説します。
【前提】国民年金とは
国民年金保険料の追納について詳しく紹介する前に、まずは国民年金の確認です。
前提として、年金には国民年金と厚生年金の2種類が存在します。
国民年金は20歳以上60歳未満の日本国民全員に納付義務がある年金、厚生年金は会社員や公務員が加入する年金です。
厚生年金の対象となる人は、国民年金の第2号被保険者に該当します。
会社員や公務員の月々の給与からは厚生年金保険料が天引きされていますが、天引きされている年金保険料は国民年金を含む金額です。
つまり厚生年金の対象者は、実際には厚生年金と国民年金の両方に加入しているのです。
厚生年金に加入すると、年金の受給時に国民年金による老齢基礎年金に老齢厚生年金が上乗せされるイメージとなります。
前述のように、厚生年金の加入者である第2号被保険者は年金保険料が毎月天引きされるため、自分で納付する必要がありません。
それ以外の人は自分で国民年金保険料を納める必要があります。
国民年金保険料の追納とは
追納とは免除・猶予を受けた保険料を後から納付する行為です。
国民年金保険料の追納とは、免除・猶予された国民年金保険料を後から納付することを意味します。
義務として設定されているわけではないため、追納するか否かは被保険者の任意となります。
国民年金保険料の免除・猶予制度とは
国民年金保険料の免除・猶予制度とは、文字通り年金保険料の支払いの免除や猶予を受けられる仕組みです。
国民年金保険料は特定の条件を満たす場合に免除や納付猶予の対象になります。
免除・猶予制度の例を紹介します。
- 法定免除
- 障害基礎年金の受給者や生活保護受給者が受けられる免除制度です。
- 申請免除
- 前年の所得が一定以下の場合に適用される免除制度です。免除申請が受理された場合に受けられます。
- 失業等による特例免除
- 会社の倒産や退職によって失業した人が受けられる制度です。
- 学生納付特例制度
- 20歳以上の学生が受けられる特例制度です。在学期間中の保険料の納付が猶予されます。
- 猶予された期間は年金受給に必要な加入期間としては扱われるものの、老齢基礎年金の年金額へは反映されません。
- 保険料納付猶予制度
- 前年所得が一定以下で申請が受理された場合に猶予を受けられる制度です。
国民年金保険料を追納するメリット

すでに紹介したように、免除や猶予を受けた国民年金保険料の追納義務はありません。
しかし、国民年金保険料の追納には2つの大きなメリットがあります。そのため、可能であれば追納するのがおすすめです。
この章では国民年金保険料を追納するメリットを詳しく解説します。
将来の年金受給額が増える
国民年金保険料を追納する大きなメリットが、将来の年金受給額が増えることです。
前提として、国民年金保険料の免除や納付猶予を受けた期間がある場合、国民年金保険料を全額納付した場合よりも年金額が低額になります。
免除や納付猶予制度を利用した場合、その制度の承認を受けていた期間の年金支給額は、全額納付した場合と比べて以下のようになります。
- 全額免除:2分の1
- 4分の3免除:8分の5
- 半額免除:8分の6
- 4分の1免除:8分の7
- 納付猶予制度:追納しなければ猶予を受けていた期間分の支給は無
国民年金保険料の追納をすれば、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけられます。
老齢基礎年金は非常に重要な収入源です。将来への備えを用意するためにも、可能であれば国民年金保険料の追納をするのが良いでしょう。
追納した年には節税効果を得られる
国民年金保険料の追納によるもう1つのメリットが、追納した年に節税効果を得られる点です。
追納で支払った年金保険料は、社会保険料控除の対象になります。
社会保険料控除とは、納税者自身または事故と生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を払った場合に受けられる所得控除です。
社会保険料控除は、もともとその年に支払い義務がある社会保険料だけでなく、追納によって納付した分も対象になります。
追納によって所得控除の対象額が増えて所得額が抑えられるため、節税につながります。
なお、国民年金保険料の追納によって節税効果を得られる税金は、所得税と住民税(所得割)の2種類です。
国民年金保険料の追納に関する注意点

最後に、国民年金保険料の追納に関する注意点を3つ紹介します。
追納には事前の申請が必要
国民年金保険料の追納は、自分の好きなタイミングでできるわけではありません。追納をするには年金事務所での申し込みが必要です。
追納の申請は、年金事務所の窓口もしくは郵送で行えます。
申請に必要な「国民年金保険料追納申込書」は日本年金機構の公式サイトでダウンロード可能です。
「ねんきんネット」で追納申込書を作成することもできます。作成した追納申込書を印刷し、窓口または郵送で提出します。
なお、申請にはマイナンバーカード(個人番号カード)が必要です。
マイナンバーカードを持っていない場合、以下の2つを用意する必要があります。
- ・通知カードや個人番号の表示がある住民票コピー等、マイナンバーが確認できる書類
- ・運転免許証、パスポート、在留カード等の身元確認書類
郵送で申請する場合、上記の本人確認書類のコピーを添付する必要があります。
マイナンバーカードは両面のコピーが必要なためご注意ください。
申請が受理されれば、追納に必要な納付書を受け取れます。
追納できるのは承認された月から10年以内の免除等期間分のみ
国民年金保険料の追納ができるのは、追納の申請が承認された月から10年以内の分のみです。
たとえば2024年の1月に追納の承認を受けた場合、追納できるのは2014年1月以降分となります。
仮に免除等期間が2013年10月から2014年12月だった場合、追納できるのは2014年1月~2014年12月分のみです。2013年10月~2013年12月分の追納はできません。
ポイントは、承認された月から10年以内という点です。追納を検討しているのであれば早めに手続きをする必要があります。
節税効果を得るには年末調整または確定申告での作業が必要
国民年金保険料の追納による節税効果を得るには、年末調整または確定申告で手続きが必要です。
追納分の社会保険料控除が自動で適用されるわけではありません。
年末調整の場合、以下の作業を行う必要があります。
- 1.社会保険料(国民年金保険料)控除証明書または納付書・領収(納付受託)証書を用意する
- 2.「給与所得者の保険料控除申告書」の「社会保険料控除欄」に、1の書類に記載されている控除額を記入する
- 3.書類を会社に提出する。原則として控除証明書と控除申告書の両方の提出が必要。
確定申告の場合、確定申告書の「社会保険料控除」に金額を記入します。
まとめ
国民年金保険料の追納には、将来の年金受給額が増える・追納した年に節税効果を得られるというメリットがあります。
支出を伴うため経済状況を考慮する必要がありますが、可能であれば追納するのがおすすめです。
国民年金保険料の追納をするには、事前に年金事務所へ追納の申請を行う必要があります。
追納できるのは追納が承認された月から10年以内の免除等期間分のみであるため、期間内に申請しましょう。
また、追納による節税効果を得るためには、年末調整または確定申告での手続きが必須です。
国民年金保険料の追納について、本記事が理解の助けになれば幸いです。
法人・個人事業主の節税対策は
BIZARQにお任せください。
全国オンライン対応・ご相談は無料です。

記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士